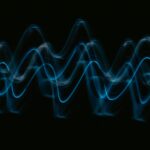2. 音データの基礎知識
2.7 波形表示やオシロスコープの例
オシロスコープは、時間とともに変化する電気信号(電圧)を画面にグラフとして描き、波形の形から信号の性質や異常を読み取るための計測器である。画面の横軸は時間、縦軸は電圧を表し、目に見えない信号の大小、速さ、形の違いを直感的に観察できるのが最大の特徴で、周波数や周期、振幅、立ち上がりの速さ、ノイズや一時的な乱れ(グリッチ)まで可視化できる。[1][2][3][4]
波形表示の基本を押さえる。オシロスコープの表示は、X(時間)、Y(電圧)、Z(輝度)の3つの要素で理解すると整理しやすい。Zは明るさ(デジタル機ではカラー階調)で、頻繁に現れる部分が濃く表示され、まれな現象を薄く表示して見つけやすくする機種もある。波形の種類としては、正弦波、矩形波(方形波)、のこぎり波、三角波、ステップ、パルス、周期的・非周期的信号などが典型例で、形の違いは含まれる周波数成分の違い(倍音や広帯域ノイズの有無)を反映する。たとえば正弦波は1つの周波数だけの滑らかな波、矩形波は急な立上がり・立下がりを持ち高周波成分が多い、のこぎり波や三角波は一定の割合で電圧が増減する、ステップは急にレベルが変わって水平に保たれる、パルスは短時間だけ高(または低)になる、と説明される。[5][6][2][7]
オシロスコープで波形を安定して表示する要はトリガ機能である。トリガとは、どのタイミングから描き始めるかを決める仕組みで、条件を満たした瞬間に波形を表示する。最も基本的なのはエッジトリガで、立ち上がり(上向き)または立ち下がり(下向き)の斜面と電圧レベルを指定し、その閾値を横切った瞬間にトリガがかかる。エッジトリガは1950年代に実装され、単発現象も安定表示できるようになった歴史があり、現在でも基本中の基本である。レベルを波形の中点(ピークtoピークの約50%)に置くのが一般的だが必須ではなく、観たい箇所に合わせて調整する。なお、レベル位置やスロープの設定しだいでは表示が左右にぶれることがあり、適切な位置取りが重要になる。[8][9][10][11][12]
正しく波形を再現するには、周波数帯域とサンプリングレート(取り込む速さ)が十分でなければならない。理論的には、信号の最高周波数の少なくとも2倍のレートでサンプリングすれば再現できる(ナイキストのサンプリング定理)が、現実の装置は無限の記録長を持たず、瞬間的な現象(グリッチ)もあるため、2倍では不十分なことが多い。補間方式を考慮すると、sinc補間では2.5倍以上、直線補間では10倍程度のサンプルレートが望ましいという実務的な目安が示されている。測定対象の最高周波数の5〜10倍程度の余裕をとる推奨もあり、エイリアシング(高域が低域に化ける誤り)を避けるには前段のローパス(アンチエイリアス)と十分なサンプルレートの組み合わせが不可欠である。サンプルレートfsと分析可能な最高周波数fmaxの関係は、理論上fmax=fs/2だが、実測では余裕を見込むのが安全だ。[13][14][15][16]
実際の表示例をイメージで整理する。正弦波を表示した場合、滑らかな山と谷が等間隔に並び、周期から周波数、山の高さから振幅が読める。矩形波では水平な高レベルと低レベルを急峻なエッジが結び、エッジの傾き(立上がり・立下がり時間)やオーバーシュート/リンギング(跳ね返り)から回路や負荷の性質(帯域・整合の良し悪し)が見て取れる。のこぎり波や三角波は線形に上昇・下降する斜面が特徴で、水平掃引回路やランプ信号の挙動確認に用いられる。ステップ応答では、指定レベルに跳ぶまでの時間、オーバーシュート、定常に落ち着くまでの減衰振動が見えるため、制御やフィルタの過渡特性評価に使える。短いパルス列はパルス幅、繰返し周期、デューティ比が読め、デジタル信号のタイミング検証に有効である。[7][4][1]
波形観測を正しく行うための実務ポイントを挙げる。第一に、プローブと本体の周波数帯域は信号の周波数成分以上が必要で、帯域が不足すると波形の角が丸まり、立上がり時間が遅く見える。第二に、サンプルレートと記録長(レコード長)は観たい現象に合わせて選ぶ。高速エッジや単発イベントを捉えるには高いサンプルレートが要り、長時間トレンドを見たいときは十分なレコード長が要る。第三に、トリガ条件(スロープ、レベル、ホールドオフなど)を適切に設定して、波形を安定させ、関心イベントの前後(プリトリガ/ポストトリガ)を確保する。第四に、シグナルインテグリティ(測定系が信号を歪めずに伝える能力)を意識し、プローブの接地リードを短くする、適正な入力インピーダンスや減衰設定を用いるなど基本に忠実にする。[10][4][5][8][13]
波形から読み取れる代表的な測定項目も理解しておくとよい。周期Tと周波数f(f=1/T)、ピークtoピーク電圧、実効値、平均値、立上がり時間(10–90%などの定義)、パルス幅、デューティ比、位相差などは、現代のデジタルオシロスコープなら自動測定機能で表示できる。複数チャネルを同時に観測して、入力と出力の遅延、クロックとデータの関係、位相のずれ(タイミングエラー)を調べる、といった典型的な解析も行える。また、Z軸のカラー階調表示を備えた機種では、発生頻度の高い波形経路が濃く表示され、珍しい逸脱(まれなジッタやグリッチ)が淡く浮かび上がるため、異常探索に役立つ。[17][4][5][1]
サンプリング方式の補足もしておく。デジタルオシロスコープにはリアルタイムサンプリングと等価時間サンプリングがあり、後者は高繰返しの同一波形を多数回の観測で時間軸をずらしながら合成することで、実効的に高い時間分解能を得る方法である。単発現象にはリアルタイム、繰返し波形の微細構造には等価時間が有効といった住み分けがある。[15][18]
最後に、学習の道筋をまとめる。まず、横軸=時間、縦軸=電圧という座標と、正弦波・矩形波・パルスなど基本波形の見かたを押さえる。次に、エッジトリガで波形を安定表示する操作(スロープとレベル設定)を体験し、関心イベントの瞬間を確実に捉える。その上で、サンプルレートと帯域の関係(最高周波数の何倍が適切か)、エイリアシングの危険とアンチエイリアスの必要性を理解し、目的の信号に見合う設定を選ぶ。最後に、自動測定や周波数・時間の各種指標を読み取り、形(波形)と数(測定値)を結びつける練習をする。これができると、音データの故障予知でも、例えばベアリングの微小なパルス的衝撃や漏れ音の広帯域化を時間波形と周波数の双方から捉え、再現性のある判断につなげられる。オシロスコープは「電圧対時間のカメラ」であり、適切なトリガと十分な帯域・サンプリングを備えれば、見たい現象を鮮明に“撮影”できる。[14][11][5][1][13][7][10][15][17] [1] https://www.tek.com/ja/documents/fact-sheet/scopebasics-mj-55z-21482-0
[2] https://www.owon.co.jp/yl.asp?NewsID=563 [3] https://www.textbook-resolver.com/oscilloscope/ [4] https://jp.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-and-advice/electrical-signals-with-an-oscilloscope [5] https://www.tek.com/ja/documents/primer/oscilloscope-basics [6] https://jm-sokki.com/column/info/what-is-an-oscilloscope/ [7] https://www.textbook-resolver.com/oscilloscope/waveform.html [8] https://tmi.yokogawa.com/jp/library/resources/measurement-tips/oscilloscope_basics/ [9] https://www.textbook-resolver.com/oscilloscope/basic-word-oscillo.html [10] https://www.tek.com/ja/documents/primer/triggering-fundamentals-pinpoint-triggering-and-event-search-mark-dpo7000-0 [11] https://www.techeyesonline.com/glossary/detail/%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC/ [12] https://faq.orixrentec.jp/kb/ja/article/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B [13] https://www.tek.com/ja/documents/primer/evaluating-oscilloscopes [14] http://owon.co.jp/yl.asp?NewsID=411 [15] https://www.techeyesonline.com/glossary/detail/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/ [16] https://www.techeyesonline.com/article/tech-column/detail/Guidance-Oscilloscope-09/ [17] https://www.rohde-schwarz.com/jp/products/test-and-measurement/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/understanding-basic-oscilloscope-operation_254512.html [18] https://www.jemima.or.jp/tech/3-03.html [19] https://download.tek.com/document/3GZ-24924-0.pdf [20] https://www.techeyesonline.com/glossary/detail/%E7%AB%8B%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8/※本ページは、AIの活用や研究に関連する原理・機器・デバイスについて学ぶために、個人的に整理・記述しているものです。内容には誤りや見落としが含まれている可能性もありますので、もしお気づきの点やご助言等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※本ページの内容は、個人的な学習および情報整理を目的として提供しているものであり、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証も行いません。本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことによって発生した損害(直接的・間接的・特別・偶発的・結果的損害を含みますが、これらに限りません)について、当方は一切責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の責任でお願いいたします。