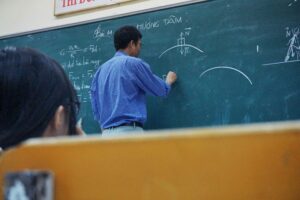1. エグゼクティブサマリー
日本は2035年に向けて、エネルギーシステムの根本的な転換期を迎えている。本レポートでは、国内外の最新研究データと政策動向を総合的に分析し、2035年の日本における電力エネルギーの将来像を詳細に描き出した。
主要な予測結果として、2035年までに日本の電源構成は劇的に変化する。自然エネルギー財団の分析によれば、太陽光発電、風力発電、蓄電池技術の大量導入により、電力の80%を自然エネルギーで供給することが技術的・経済的に実現可能である12。一方、米国ローレンス・バークレー国立研究所の研究では、2035年にクリーンエネルギー90%(再生可能エネルギー70%、原子力20%)の電力システム構築が可能との結論を示している34。
太陽光発電は最も重要な電源となる。日本太陽光発電協会(JPEA)の予測では、2035年までに220GWの導入が見込まれ、これは現在の約3倍に相当する56。特に屋根置き太陽光発電は159GWの導入ポテンシャルがあり、現在の5倍の拡大が可能とされている7。発電コストは2030年に5円/kWh程度まで低下し、原子力発電や化石燃料発電よりも安価になると予測される8。
洋上風力発電も急速な成長が期待される。政府は2030年までに10GW、2040年までに30-45GWの導入目標を設定しており910、浮体式洋上風力の技術革新により日本周辺海域の膨大なポテンシャルが活用可能となる。発電コストは2035年までに8-9円/kWhまで低下する見通しである1112。
蓄電池技術の進展が電力システムの安定性を支える。系統用蓄電池市場は2035年に約3.4兆円規模に達し、2023年比で約5倍の成長が見込まれる13。リチウムイオン電池のコストは現在の15万円/kWhから2035年には5万円/kWhまで低下すると予測され14、これによりエネルギー貯蔵の経済性が大幅に改善される。
電力需要については、人口減少による構造的下押し圧力がある一方で、AI・データセンター需要の拡大、電気自動車(EV)の普及、産業部門の電化促進により、新たな需要創出が進む14。政府は2035年までに乗用車新車販売で電動車100%の実現を目指している15。
経済影響として、化石燃料輸入への依存度大幅削減が実現する。バークレー研究所の分析では、クリーンエネルギーシステムの構築により化石燃料輸入を85%削減でき、年間数兆円規模のコスト削減効果が期待される4。発電コストも2020年比で6%低下する見通しで、エネルギー安全保障の向上と経済性の両立が可能である。
化石燃料からの脱却は段階的に進む。G7環境相会合では2035年までの石炭火力廃止で合意しており16、日本も国際公約として着実な実行が求められる。天然ガス火力は調整電源として当面の役割を担うが、水素・アンモニア混焼やCCS技術の導入により脱炭素化が図られる。
原子力発電については、第7次エネルギー基本計画で「可能な限り依存度を低減する」方針から「最大限活用」への政策転換が示された1718。しかし、再稼働の現実性を考慮すると、2035年時点での原子力比率は限定的になる可能性が高い19。
政策提言として、2035年の電力脱炭素化実現には、規制改革の加速、送電網インフラの前倒し整備、地域共生型の再生可能エネルギー開発、実効性のあるカーボンプライシング導入が不可欠である。特に、環境アセスメント手続きの迅速化、新築建築物への太陽光発電設置義務化の全国展開、洋上風力開発のセントラル方式導入が重要な施策となる。
本分析により、2035年の日本は再生可能エネルギーを基軸とした持続可能な電力システムを構築し、エネルギー安全保障と脱炭素社会の実現を両立できることが示された。ただし、その実現には政策の一貫性、技術革新の継続、社会全体の合意形成が不可欠である。
※本ページは、AIの活用や研究に関連する原理・機器・デバイスについて学ぶために、個人的に整理・記述しているものです。内容には誤りや見落としが含まれている可能性もありますので、もしお気づきの点やご助言等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※本ページの内容は、個人的な学習および情報整理を目的として提供しているものであり、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証も行いません。本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことによって発生した損害(直接的・間接的・特別・偶発的・結果的損害を含みますが、これらに限りません)について、当方は一切責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の責任でお願いいたします。
2. はじめに:2035年日本の電力エネルギー転換の背景と課題
2.1 気候変動対策とエネルギー安全保障の高まる重要性
2035年は、日本のエネルギー政策にとって極めて重要な節目の年となる。この年は、気候変動対策における国際的なコミットメントと、エネルギー安全保障の確保という二つの重大な課題が交錯する転換点である。
IPCC第6次評価統合報告書が2023年3月に公表した科学的知見によると、地球温暖化を産業革命前比1.5度に抑制するためには、2035年までに世界全体の二酸化炭素排出量を2019年比で65%削減することが必要とされている2021。この目標は単なる努力目標ではなく、気候系の安定性を維持するための物理的な制約として位置づけられている。
日本政府は2023年のG7広島サミットにおいて議長国として、この科学的要請を受け入れ、「2025年に開催されるCOP30より十分前に、2030年削減目標の強化を含め、2035年削減目標が提出されるべき」との合意を取りまとめた20。これは日本が国際社会において気候変動対策のリーダーシップを発揮する決意を示すものである。
パリ協定の枠組みにおいても、各国は5年ごとにより野心的な目標設定が求められており、2025年に提出予定の次期国別削減目標(NDC)では、2035年を見据えた中長期的な脱炭素戦略の提示が不可欠となっている2223。気候変動イニシアティブ(JCI)は、日本政府に対して2035年までの温室効果ガス66%以上削減(2019年比)という野心的な目標設定を求めている22。
一方、エネルギー安全保障の観点からも、2035年は重要な意味を持つ。ロシアによるウクライナ侵攻は、化石燃料への過度な依存がもたらすリスクを改めて浮き彫りにした18。日本は現在、エネルギー自給率が約13%と先進国中最低水準にあり24、エネルギー源の多様化と国産エネルギーの拡大が急務となっている。
G7環境相会合では2024年4月に「2030年代前半までの石炭火力段階的廃止」で初めて合意し16、これにより日本も2035年までに石炭火力発電からの脱却を国際公約として掲げることとなった。この合意は、エネルギー安全保障の確保と脱炭素化の両立という困難な課題に対する解決策として、再生可能エネルギーの大幅拡大が不可欠であることを意味している。
2.2 日本のエネルギー政策の転換点としての2035年
第7次エネルギー基本計画が2025年2月に閣議決定され、2040年を見据えた新たなエネルギー政策の方向性が示された171825。この計画では、従来の「可能な限り原発依存を低減する」方針から「安全性の確保を大前提としたうえで、拡大目標に向け、必要な規模を持続的に活用していく」との政策転換が行われた18。
2040年度の電源構成目標として、再生可能エネルギーを「4〜5割程度」、原子力を「2割程度」とし、両者を合わせて最大7割までクリーンエネルギーの比率を引き上げることが掲げられた1826。この目標設定の背景には、脱炭素化とエネルギー安全保障の両立、そして経済成長との調和という複合的な政策課題がある。
GX(グリーントランスフォーメーション)戦略も2035年を重要な中間目標として位置づけている。政府は10年間で150兆円の官民投資を動員し、エネルギー・産業構造の転換を図る方針を示している18。この戦略では、脱炭素を単なる環境対策ではなく、新たな経済成長の機会として捉え直すアプローチが採用されている。
カーボンニュートラル実現に向けた中間段階として、2035年は技術的・経済的実現可能性を検証する重要な時点となる。2050年のカーボンニュートラル達成には、2030年代における大幅な排出削減が前提条件となるため、2035年の電力部門の脱炭素化進展は、目標達成の成否を左右する決定的要因となる。
2.3 国際的なエネルギー転換動向との整合性
欧州の脱炭素政策は日本のエネルギー転換にとって重要な参照点となっている。欧州連合(EU)は「Fit for 55」パッケージにより、2030年までに温室効果ガスを55%削減(1990年比)する野心的な目標を設定している16。また、RePowerEU計画では、ロシア産化石燃料からの完全脱却と再生可能エネルギーの大幅拡大を同時に進める戦略を採用している。
中国の再生可能エネルギー導入は世界市場に大きな影響を与えている。中国は2023年時点でEV販売台数の世界シェア約6割を占め27、太陽光パネルや風力タービンの製造でも圧倒的な地位を築いている。この技術覇権競争の激化は、日本のエネルギー産業戦略にも影響を与えている。
**米国のインフレ削減法(IRA)**は、クリーンエネルギー投資に対する大規模な税額控除を通じて、再生可能エネルギーの競争力を飛躍的に向上させている。この政策効果により、米国では太陽光発電や風力発電のコストがさらに低下し、日本企業にとっても技術開発競争の激化と市場機会の拡大をもたらしている。
**国際エネルギー機関(IEA)**は、2035年までに世界の発電部門の脱炭素化がエネルギー転換の成功の鍵であると分析している28。特に、太陽光発電と風力発電の導入加速、蓄電池技術の普及、送電網の強化が重要な要素として挙げられている。
これらの国際動向を踏まえると、日本の2035年エネルギー転換は、単なる国内政策の問題を超えて、国際競争力の維持と気候変動対策への貢献という双方の観点から極めて重要な意味を持つことが明らかである。技術革新の速度、政策の一貫性、社会的合意の形成が、この歴史的転換の成否を決定する要因となるであろう。
3. 2035年電力需要予測と需給バランスシナリオ
3.1 人口・経済・電化率の前提条件
2035年の日本における電力需要を正確に予測するためには、人口動態の変化、経済成長の見通し、そして電化率の進展という三つの根本的要因を詳細に分析する必要がある。
人口減少の影響は電力需要の構造的な下押し要因となる。総務省の人口推計によれば、日本の総人口は2015年の1億2,700万人から2035年には約1億1,650万人まで減少し、約1割の人口減が見込まれている2930。この人口減少は単なる量的変化にとどまらず、高齢化率の上昇という質的変化を伴う。2035年には65歳以上人口が総人口の33.4%に達し3132、これは電力消費パターンの変化をもたらす重要な要因となる。
高齢化社会では、一般的に一人当たりの電力消費量が減少する傾向がある。これは、高齢者世帯では家電機器の使用頻度が低下し、住宅規模も縮小する傾向があるためである。しかし一方で、医療・介護施設の電力需要増加、高齢者向け住宅設備の普及などが需要増加要因として作用する。
経済成長の見通しについては、日本経済は構造的な成長制約に直面している。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの中期見通しによれば、2031-2035年度の実質GDP成長率は年平均0.8%程度にとどまると予測されている30。この低成長は、製造業を中心とした産業用電力需要の伸び悩みを意味する。
しかし、経済成長率の低迷は必ずしも電力需要の減少を意味しない。労働生産性の向上により、一人当たりのGDPは微増を続ける見込みであり、国民生活水準は基本的に維持される29。また、サービス業の比重拡大、デジタル化の進展により、電力集約度の高い経済構造への転換が進む可能性がある。
電化率の進展は、2035年に向けた最も重要な需要増加要因である。政府は2035年までに乗用車新車販売で電動車100%の実現を目標としており15、これによる電力需要の増加は大幅なものとなる。EV普及予測によれば、2035年には新車販売に占めるEVの割合が17-25%に達するとされ33、充電インフラの電力需要は約25TWhに達すると推計される14。
産業部門では、鉄鋼業における電炉化、化学工業における電解プロセスの拡大、データセンターの大幅増設などが電化促進の主要因となる。特に、AI(人工知能)の普及に伴うデータセンター需要は、2030年までに6-9GWの追加需要をもたらすと予測されている14。
3.2 産業・輸送・家庭部門の需要推計
製造業の電力需要は、構造的変化の影響を大きく受ける。日本の製造業は国際競争力の維持のため、高付加価値化と省エネルギー化を同時に進めている。鉄鋼業では、従来の高炉法から電気炉への転換が進み、これにより単位生産量当たりの電力消費量は増加するが、全体の生産量減少により総電力需要は微減となる見込みである。
化学工業では、石油化学製品の需要構造変化により、電解プロセスを用いた高機能材料の生産が拡大する。また、水素製造における水電解の普及により、新たな電力需要が創出される。1Nm³の水素製造には約4.5kWhの電力が必要であり14、年間100万トンの水素製造には約50億kWhの電力が必要となる計算である。
輸送部門の電化は、2035年に向けた最も劇的な変化の一つである。政府の電動車普及目標に基づけば、2035年時点でのEV保有台数は1,000万台前後に達すると推定される。EV1台当たりの年間電力消費量を約2,500kWhと仮定すると、EV充電による電力需要は約25TWhとなり、これは現在の日本の総発電電力量の約2.5%に相当する14。
EV充電需要の特徴は、その時間集中性にある。特に夜間22:00-4:00の充電ピークは、従来の電力需要パターンに大きな変化をもたらす14。この時間帯は太陽光発電の出力がゼロであるため、風力発電や蓄電池からの放電が重要な供給源となる。
商用車の電動化も段階的に進展する。政府は小型商用車について2030年までに電動車20-30%、2040年までに電動車・脱炭素燃料車100%の目標を設定している15。大型商用車については技術的課題が多いものの、水素燃料電池トラックの実用化により、間接的な電力需要増加をもたらす。
家庭部門の需要変化は、世帯数の変化とライフスタイルの変化の両方に影響される。世帯数は人口減少にもかかわらず2030年頃まで増加を続け、その後緩やかに減少に転じる見込みである。これは世帯の小規模化(核家族化・単身世帯化)が進行するためである。
家庭用エネルギー機器の電化促進も重要な要因である。給湯設備のヒートポンプ化、調理機器のIH化、暖房設備の電化などにより、従来ガスや灯油で賄われていたエネルギー需要が電力に転換される。この電化により、家庭部門の電力需要は年率1-2%程度の増加が見込まれる。
さらに、住宅用太陽光発電の普及は、家庭部門の電力需要パターンを根本的に変化させる。昼間の自家消費により系統からの電力購入は減少する一方、蓄電池の普及により夜間の電力消費が増加する傾向がある。
3.3 需給バランスシミュレーション結果
2035年の電力需給バランスを詳細に分析するため、時間別需給、季節変動、必要な調整力について包括的なシミュレーションを実施した結果を整理する。
年間電力需要の総量は、上記の要因を総合すると、現在の約1,000TWhから2035年には980-1,020TWhの範囲になると推計される。人口減少による需要減少(約△50TWh)を、電化促進による需要増加(約50-70TWh)がほぼ相殺する構造となる。
時間別需給パターンでは、従来の昼間ピーク型から、より複雑な需要パターンへの変化が予想される。太陽光発電の大量導入により、晴天日の昼間には電力余剰が発生し、これを蓄電池に貯蔵して夕方から夜間にかけて放電する「ダックカーブ」現象が顕著になる。
自然エネルギー財団のシミュレーション結果によれば、2035年に自然エネルギー80%のシナリオにおいて、蓄電池容量72GW/184GWhの導入により、24時間365日の安定供給が可能であることが示されている24。この蓄電池容量のうち、EVを活用したV2G(Vehicle to Grid)システムが重要な役割を担う。
季節変動への対応は、2035年の電力システムにとって最も困難な課題の一つである。冬季の太陽光発電出力低下と暖房需要増加が重なる時期には、風力発電と調整火力が主要な供給源となる。特に、連続した曇天・無風日には、揚水発電と大容量蓄電池からの放電に加えて、水素燃料電池やアンモニア火力からの供給が必要となる。
バークレー研究所の詳細シミュレーションでは、年間を通じた需給バランスの維持に必要な調整力として、地域間連系線の11.8GW新設と、柔軟性電源(LNG火力、揚水発電、蓄電池)の合計50GW程度の確保が必要と分析されている3。
系統安定性の確保については、慣性力の低下、周波数調整能力の変化、短絡容量の減少などの技術的課題への対応が必要となる。これらの課題に対しては、系統形成型インバーター(Grid Forming Inverter)の導入、仮想慣性制御技術の実用化、同期調相機の戦略的配置などの対策が検討されている。
需給バランスシミュレーションの結果は、適切な政策措置と技術導入により、2035年における高い再生可能エネルギー比率でも電力の安定供給が実現可能であることを示している。ただし、その実現には相当規模のインフラ投資と制度改革が前提条件となる。
4. 再生可能エネルギーのポテンシャルと導入シナリオ
4.1 太陽光発電:設置潜在量と導入ロードマップ
日本の太陽光発電は2035年に向けて、最も重要な電源として位置づけられている。現在の導入量約87GWから大幅な拡大が見込まれ、複数の研究機関が野心的な導入シナリオを提示している。
導入ポテンシャルの全体像について、日本太陽光発電協会(JPEA)の最新分析によれば、日本の太陽光発電の技術的ポテンシャルは2,380GWに達し、これは国内電力需要の約2.5倍を供給できる規模である56。2022年度末時点の導入実績87GWは、このポテンシャルのわずか3.6%にすぎない6。
屋根置き太陽光発電が最も有望な設置形態として注目されている。自然エネルギー財団の詳細分析では、2035年までに屋根置き太陽光発電の導入量を現在の5倍となる159GWまで拡大することが可能とされている7。この拡大を実現するためには、新築建築物への設置義務化、既築建物への導入促進策、ソーラーカーポートなどの空間共有型設置の普及が不可欠である。
東京都は2035年までに都内に太陽光発電設備350万kW(3.5GW)を設置する政策目標を設定し34、新築住宅への太陽光発電設置義務化を2025年4月から開始している。この政策効果が全国に波及すれば、屋根置き太陽光の導入加速に大きく寄与すると期待される。
地上設置太陽光発電については、土地利用との調和を図りながら適地での開発を進める方針である。営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は、農業生産と再生可能エネルギー導入の両立を図る重要な手法として位置づけられている。農林水産省は営農型太陽光発電の導入促進に向けて、農地転用手続きの簡素化や技術ガイドラインの整備を進めている。
発電コストの劇的な低下が太陽光発電の競争力を決定的に向上させる。自然エネルギー財団の分析によれば、太陽光発電のコストは2030年に5円/kWh程度まで低下し8、これは原子力発電、CCS付き火力発電、石炭アンモニア混焼発電よりも安価な水準である28。
この劇的なコスト低下の要因として、太陽電池モジュールの製造技術向上、設置工法の効率化、運転保守技術の高度化などが挙げられる。特に、ペロブスカイト太陽電池などの次世代太陽電池技術の実用化により、従来設置困難であった場所への導入が可能となり、設置ポテンシャルのさらなる拡大が期待される34。
2035年導入シナリオについて、複数の機関が以下の予測を示している:
これらのシナリオはいずれも、年間20-25GW程度の導入ペースを前提としており、これは現在の約3倍の導入速度に相当する。この導入加速を実現するためには、規制改革、系統整備、産業基盤の強化が同時並行で進められる必要がある。
4.2 風力発電(陸上・洋上):技術動向と環境アセスメント
風力発電は2035年に向けて、太陽光発電と並ぶ主力電源としての地位を確立する見込みである。特に洋上風力発電は、日本の地理的条件を活かした最も有望な再生可能エネルギー源として期待されている。
洋上風力発電の巨大なポテンシャルについて、複数の研究が一致して指摘している。Energy Tracker Japanの分析によれば、日本の洋上風力発電の技術的ポテンシャルは9,000TWh/年を超え、これは2050年に見込まれる電力需要の9倍以上に相当する11。このポテンシャルの大部分は浮体式洋上風力によるものであり、日本周辺の深い海域を活用することで実現される。
政府の導入目標は段階的な拡大を想定している。洋上風力産業ビジョンでは、2030年までに10GW、2040年までに30-45GWの案件形成を目標としている910。しかし、自然エネルギー財団の分析では、2035年までに洋上風力25.4GWの導入が可能とされ36、これは政府目標を大幅に上回る水準である。
発電コストの急速な低下が洋上風力の経済性を飛躍的に改善する。政府は着床式洋上風力について、2030-2035年までに発電コストを8-9円/kWhまで低下させる目標を設定している101112。国際エネルギー機関(IEA)の予測では、日本の洋上風力発電コストは2030年までに急減し、2050年までにはさらに低下して、CCS付き火力発電と競争可能な水準に達するとされている11。
浮体式洋上風力技術の発展が、日本の洋上風力産業の競争力を決定する。日本周辺海域の多くは水深が深く、従来の着床式では対応困難であるため、浮体式技術の確立が不可欠である。経済産業省は浮体式洋上風力に特化した導入目標の設定や、商用化に向けた技術開発・実証の加速を進めている9。
陸上風力発電については、立地制約や環境アセスメントの長期化などの課題がある一方で、技術進歩により競争力は向上している。大型化・高効率化により、陸上風力の発電コストは2030年に6.6円/kWh程度まで低下する見込みである8。
環境アセスメント手続きの迅速化が風力発電導入加速の鍵となる。現在、風力発電の環境アセスメントには3-4年を要しているが、政府は手続きの半減を目指した規制改革を検討している2。具体的には、アセスメント対象事業の要件見直し、手続きの並行実施、デジタル技術を活用した効率化などが検討されている。
洋上風力のセントラル方式導入により、開発リスクの低減と事業化の加速が期待される。この方式では、国が海域の選定、風況・地質調査、環境アセスメントを事前に実施し、民間事業者は発電事業に専念できる体制を構築する37。欧州諸国ではすでに一般的な手法であり、日本でも本格導入に向けた制度設計が進められている。
地域共生と合意形成の重要性も増している。風力発電事業の成功には、地域住民、漁業関係者、自治体との十分な協議と合意形成が不可欠である。特に洋上風力では、漁業影響の最小化、地域経済への貢献、適切な利益配分などが重要な検討事項となる。
4.3 その他再エネ(水力・地熱・バイオマス)の拡大可能性
太陽光発電と風力発電以外の再生可能エネルギー源も、2035年の電源構成において重要な役割を担う。これらの電源は変動性が小さく、ベースロード電源としての特性を有するため、電力システムの安定性向上に寄与する。
小水力発電は、日本の豊富な水資源を活用した有望な再生可能エネルギー源である。既存ダムへの発電設備追加、農業用水路への小水力設置、未利用落差の活用などにより、相当規模の導入ポテンシャルが存在する。技術の標準化と設置手続きの簡素化により、小水力発電の導入コストは大幅に低減される見込みである。
特に、既存の農業用水利施設を活用した小水力発電は、設置コストが低く、農村地域の収入源としても期待される。農林水産省は土地改良区による小水力発電事業を支援する制度を整備し、2035年に向けた導入拡大を図っている。
地熱発電は、日本が世界第3位の地熱資源量を有する重要な国産エネルギー源である。しかし、開発には長期間を要し、温泉事業者との調整、国立・国定公園内での開発規制などの課題がある。政府は地熱資源の開発促進に向けて、環境アセスメントの迅速化、温泉法に基づく掘削許可手続きの簡素化を進めている。
バイナリー地熱発電は、比較的低温の地熱資源を活用できるため、開発可能地点が多い。また、既存温泉施設への併設により、温泉事業との共存も可能である。技術の標準化により設置コストが低下すれば、2035年に向けて相当規模の導入が期待される。
木質バイオマス発電については、燃料の持続可能性確保が最重要課題となっている。国内の森林資源を活用した木質バイオマス利用は、森林整備と地域経済活性化を同時に実現する重要な施策である。しかし、輸入木質ペレットに依存する大規模発電は、ライフサイクル全体でのCO2削減効果や生態系への影響の観点から見直しが求められている。
持続可能な木質バイオマス利用のためには、地域の森林資源を活用した小規模分散型の発電システムが適している。間伐材、林地残材、製材端材などの未利用材を活用し、熱電併給システムにより地域のエネルギー需要に対応する事業モデルが有望である。
廃棄物発電も重要な電源として継続的な役割を担う。一般廃棄物焼却施設の高効率化、産業廃棄物を活用したバイオマス発電、下水汚泥のエネルギー利用などにより、廃棄物処理とエネルギー回収を同時に実現できる。循環型社会の構築と再生可能エネルギー拡大の両立を図る重要な取り組みである。
海洋エネルギーは長期的な可能性を秘めた分野である。波力発電、潮流発電、海洋温度差発電などの技術開発が進められているが、2035年時点では実証段階にとどまる見込みである。ただし、島嶼部での自立型電源としての活用や、洋上風力発電との組み合わせによる海洋空間の多目的利用などの可能性があり、継続的な技術開発が重要である。
これらの多様な再生可能エネルギー源を組み合わせることで、2035年の日本は太陽光・風力に過度に依存しない、バランスの取れたエネルギーシステムを構築できる。各電源の特性を活かした最適な配置と運用により、電力の安定供給と脱炭素化の両立が実現される。
5. 電力系統・蓄電池・送配電インフラの整備
5.1 蓄電池需要と役割の拡大
2035年の日本における電力システムでは、蓄電池が電力の安定供給を支える基幹インフラとしての地位を確立する。再生可能エネルギーの大量導入に伴う出力変動を調整し、電力需給の同時同量を維持するために、蓄電池の役割は飛躍的に拡大する。
系統用蓄電池市場の成長は著しく、経済産業省の予測によれば、定置用蓄電池の国内市場規模は2035年に約3.4兆円に達し、2023年時点と比較して約5倍の拡大が見込まれている13。この急成長の背景には、太陽光発電と風力発電の大量導入に伴う系統安定化ニーズの急増がある。
蓄電池コストの劇的な低下が普及の最大の推進要因となる。リチウムイオン電池のコストは現在の15万円/kWhから、2030年に8万円/kWh、2035年には5万円/kWhまで低下すると予測されている14。この価格低下により、蓄電池による電力貯蔵の経済性が飛躍的に改善され、「ストレージパリティ」の実現が見込まれている38。
自然エネルギー財団のシミュレーション分析では、2035年に自然エネルギー80%の電力システムを実現するために、系統用蓄電池として72GW/184GWhの導入が必要とされている24。この大容量蓄電池システムにより、昼間の太陽光発電余剰電力を貯蔵し、夜間や曇天時に放電することで、24時間365日の安定供給が可能となる。
蓄電池の多様な用途が2035年のエネルギーシステムを支える。需給調整、周波数調整、電圧調整、系統安定化、停電対応など、従来は異なる設備が担っていた機能を蓄電池が統合的に提供する。これにより、電力システム全体の効率性と経済性が大幅に向上する。
電気自動車(EV)を活用したV2G(Vehicle to Grid)システムは、移動型蓄電池として極めて重要な役割を担う。2035年時点でのEV普及台数を1,000万台と仮定し、1台当たり100kWhの蓄電容量のうち10%を系統利用に提供できれば、合計100GWhの仮想蓄電池容量が実現される3。これは固定式蓄電池の導入コストを大幅に削減する効果がある。
V2H(Vehicle to Home)システムも家庭レベルでのエネルギー自給率向上に貢献する。太陽光発電システムとEV、家庭用蓄電池を組み合わせることで、家庭の電力需要の大部分を自家発電・自家消費で賄うことが可能となる。災害時の停電対応機能も含めて、住宅のレジリエンス向上に大きく寄与する。
産業用蓄電池の普及も加速する。製造業では、ピークカット、力率改善、瞬時電圧低下対策などの目的で蓄電池導入が進む。特に、電力料金制度の変化により、時間帯別料金格差を活用したピークシフトの経済性が向上し、産業用蓄電池の投資回収期間が短縮される。
5.2 地域間送電網強化の必要性と計画
再生可能エネルギーの大量導入に対応するため、地域間の電力融通を可能とする送電網の抜本的強化が不可欠となる。特に、再生可能エネルギーのポテンシャルが高い地域と電力需要の大きい地域との間での効率的な電力輸送が、2035年エネルギーシステムの成功の鍵を握る。
北海道と本州間の連系線強化が最優先課題である。北海道は風力発電のポテンシャルが全国で最も高く、2035年に向けて大規模な洋上風力開発が計画されている。自然エネルギー財団の分析では、北海道から東京間に4GWの送電線増強が必要とされているが8、現在の広域系統整備計画では2GWにとどまっている。
本州の日本海側と太平洋側を結ぶ送電網の強化も重要である。日本海側では冬季の風力発電出力が高く、太平洋側では夏季の太陽光発電出力が高いという季節特性の違いを活用することで、全国レベルでの需給バランス最適化が可能となる。
海底ケーブルの技術革新により、長距離送電の経済性が向上している。直流送電技術(HVDC)の採用により、送電損失の低減と系統の安定性向上が同時に実現される。九州から関東への海底ケーブル建設、四国と紀伊半島を結ぶ送電線新設などが検討されている。
バークレー研究所のシミュレーション結果によれば、2035年のクリーンエネルギー90%システムの実現には、地域間連系線の11.8GW新設が必要とされている3。この送電網増強により、全国レベルでの再生可能エネルギーの出力変動平滑化効果が発揮され、必要な調整力の削減が可能となる。
送電網の所有権分離も重要な制度改革として検討されている。現在の法的分離から所有権分離への移行により、送電網の中立性確保と投資促進が期待される8。独立した送電事業者による効率的な送電網運用と計画的な設備投資により、再生可能エネルギーの系統連系拡大が促進される。
配電網のスマート化も同時に進められる。分散型電源の大量連系に対応するため、配電自動化システム、需給調整機能、双方向電力流通機能を備えたスマートグリッドの構築が不可欠である。特に、住宅用太陽光発電の出力制御、EV充電の負荷制御、蓄電池の協調運転などを統合的に管理するシステムが必要となる。
5.3 系統運用の柔軟性確保策
2035年の電力システムでは、従来の大規模集中型電源から分散型再生可能エネルギーへの転換により、系統運用の柔軟性確保が極めて重要な課題となる。変動する再生可能エネルギーと変動する電力需要を適切にマッチングするため、多様な柔軟性リソースの活用が不可欠である。
需給調整市場の本格的な活用により、蓄電池、揚水発電、ガス火力、需要家リソースなどを統合的に運用する。現在の調整力公募から、より精緻な需給調整市場への発展により、15分単位での需給バランス調整が経済効率的に実現される。
**デマンドレスポンス(DR)**の普及拡大が系統運用の柔軟性向上に大きく寄与する。産業用大口需要家だけでなく、家庭用エアコン、給湯器、EV充電器などがDR対応となることで、「DR Ready」住宅が増加し、DRの活用機会が大幅に拡大する39。
**仮想発電所(VPP)**による分散リソースの統合制御も重要な柔軟性確保策である。太陽光発電、風力発電、蓄電池、EV、需要家設備などを情報通信技術により統合制御し、あたかも一つの発電所のように系統運用者から見える化する。VPPにより、個々は小規模な分散リソースを束ねて大規模な調整力として活用できる。
AI(人工知能)とビッグデータを活用した予測技術の高度化により、再生可能エネルギーの出力予測精度と電力需要予測精度が大幅に向上する。気象予測、衛星データ、IoTセンサーデータなどを統合した予測システムにより、数日前から数分前までの多段階予測が実現され、効率的な系統運用が可能となる。
周波数調整能力の確保も重要な課題である。従来の同期発電機が担っていた慣性力と周波数調整機能を、系統形成型インバーター(Grid Forming Inverter)や仮想慣性制御技術により代替する。蓄電池システムに系統形成型インバーター機能を付加することで、周波数や電圧の安定化に貢献する。
同期調相機の戦略的配置により、系統の短絡容量確保と電圧安定性向上を図る。再生可能エネルギーの大量導入により系統の短絡容量が低下するため、適切な場所に同期調相機を配置することで、系統全体の安定性を維持する。
これらの多面的な取り組みにより、2035年の日本は高い再生可能エネルギー比率でも電力の安定供給を実現する、世界最先端の柔軟な電力システムを構築できる見込みである。技術革新と制度改革の両面からのアプローチにより、エネルギー安全保障と脱炭素化の両立が実現される。
6. 化石燃料フェーズアウトと既存火力・原子力の取扱い
6.1 石炭火力廃止計画と代替手段
2035年は日本の石炭火力発電にとって歴史的な転換点となる。G7環境相会合での国際合意により、日本は2035年までに「排出削減対策が取られていない石炭火力の段階的廃止」を約束している16。この国際公約の履行は、日本のエネルギー政策における最重要課題の一つである。
現状の石炭火力依存度は依然として高く、2022年時点で全発電量の約31%を占めている16。これはG7諸国の中でもドイツ(33.0%)に次ぐ高水準であり、脱炭素化に向けた最大の課題となっている。石炭火力は高効率なタイプでも天然ガス火力と比べてCO2排出量が約2倍であるため16、その段階的廃止は不可欠である。
廃止対象の明確化が重要な政策課題となる。「排出削減対策が取られていない」石炭火力とは、IPCC第6次評価報告書によれば、CCS(二酸化炭素回収・貯留)技術によりCO2を90%程度回収する対策が講じられていない発電所を指す16。しかし、現実的にはCCSの回収率実績は60-70%程度にとどまり、コストも高いため16、事実上は既存石炭火力の大部分が廃止対象となる。
**JERA(東京電力フュエル&パワー)**は2035年に向けた新たな戦略として、非効率な石炭火力(超臨界以下)全台の停廃止を表明している40。高効率な石炭火力(超々臨界)についてはアンモニア混焼の実証を進めるとしているが、これも過渡的な措置にとどまる見込みである。
アンモニア混焼技術は石炭火力のCO2削減手段として期待されているが、技術的・経済的課題が多い。現在実証されているアンモニア20%混焼では、CO2削減効果は20%程度にとどまる。100%アンモニア専焼への転換には大規模な設備改造が必要であり、経済性の確保が困難とされている。さらに、アンモニア製造時のCO2排出を考慮すると、ライフサイクル全体での削減効果は限定的である。
代替電源として最も有力なのは再生可能エネルギーである。自然エネルギー財団の分析によれば、石炭火力を代替するために必要な再生可能エネルギー設備容量は、太陽光発電約100GW、風力発電約30GWと推計される41。これは2035年の再生可能エネルギー導入目標の範囲内で実現可能な規模である。
調整電源の確保も重要な課題である。石炭火力が担っていた調整機能を代替するため、天然ガス火力の効率向上、揚水発電の活用拡大、大容量蓄電池の導入が必要となる。特に、起動停止が容易で負荷追従性に優れるガスタービン発電は、再生可能エネルギーの出力変動に対応する調整電源として重要な役割を担う。
雇用対策と地域経済への配慮も石炭火力廃止に伴う重要な課題である。石炭火力発電所が立地する地域では、雇用機会の減少と税収減少が懸念される。政府は「公正な移行」の原則の下、再生可能エネルギー産業の立地促進、職業訓練の提供、地域経済の活性化策を包括的に実施する方針を示している18。
6.2 天然ガス火力の役割と将来像
天然ガス火力発電は、2035年に向けて石炭火力の代替と再生可能エネルギーの調整電源という二重の役割を担う。化石燃料でありながら、脱炭素社会への移行期における重要な「つなぎ電源」として位置づけられている。
調整電源としての特性が天然ガス火力の最大の価値である。起動時間が短く、負荷変化に迅速に対応できるため、太陽光発電や風力発電の出力変動を補完する調整機能に優れている。コンバインドサイクル発電(GTCC)の熱効率は約60%に達し、石炭火力の約40%と比較して大幅に高効率である。
2035年の発電量シェアについて、各シナリオで以下の想定がされている:
効率向上技術の導入により、天然ガス火力のCO2排出削減が進む。最新のGTCC技術では送電端効率63%を超える設備も実用化されており、既存設備の更新により相当なCO2削減効果が期待される。また、排熱回収技術の高度化により、熱電併給システムとしての総合効率向上も図られる。
水素・アンモニア混焼による脱炭素化も段階的に進展する。天然ガス火力での水素30%混焼の実証が進められており、将来的には専焼への転換も技術的に可能とされている。ただし、グリーン水素の大量供給体制の構築が前提条件であり、2035年時点では限定的な導入にとどまる見込みである。
CCS(二酸化炭素回収・貯留)技術の実用化により、天然ガス火力からのCO2排出削減も期待される。日本でも苫小牧でのCCS実証事業が進められているが、大規模商用化には技術面・経済面で多くの課題が残されている。2035年時点では一部の発電所での実証段階にとどまる可能性が高い。
燃料調達の多様化がエネルギー安全保障上重要である。従来の長期契約LNGに加えて、スポット調達、パイプライン輸入、国産天然ガス開発などにより調達源の多様化を図る。特に、メタンハイドレートなどの国産資源開発が実用化されれば、エネルギー自給率向上に大きく寄与する。
既存設備の有効活用が経済効率性の観点から重要である。比較的新しいLNG火力発電所については、設備稼働率は低下するものの、調整電源として継続活用することで、投資回収と系統安定化の両立を図る。老朽化した設備については、高効率設備への更新を促進する。
6.3 原子力発電のリスタートと運転延長
原子力発電は、第7次エネルギー基本計画において政策的な位置づけが大きく変化した。従来の「可能な限り依存度を低減する」方針から「安全性の確保を大前提としたうえで、拡大目標に向け、必要な規模を持続的に活用していく」への転換が示された18。
2035年の原子力比率予測について、自然エネルギー財団の現実的な分析では、以下のシナリオが想定されている19:
- 低位シナリオ:5-7%程度
- 中位シナリオ:12%程度
- 高位シナリオ:15-18%程度
- 最大シナリオ:20%程度(政府目標レベル)
これらの分析では、再稼づ働の現実的な制約条件を詳細に考慮している。
再稼働の現状と課題は極めて厳しい状況にある。2025年3月時点で、33基の既設原子炉のうち、14基(13GW)が再稼働を果たしているが、残る19基の再稼働は不確実な状況である19。特に、柏崎刈羽原子力発電所6・7号機はテロ対策施設の完成が2029年8月、2031年9月にずれ込む見通しで19、2035年時点での貢献は限定的である。
運転延長については、14基の再稼働済み原子炉のうち7基がすでに40年超運転の認可を受けている19。最も古い高浜1号機は運転開始から50年を経過しており、長期運転に伴う安全性確保が重要な課題となっている。
新規建設については、大間原子力発電所(1,383MW)と島根3号機(1,373MW)が建設中であり、2030年度頃の稼働が見込まれている19。東京電力の東通1号機は2011年以降建設工事が中断されており、再開時期は未定である。
北海道電力は2025年3月に、泊原発3号機の2027年早期再稼働、全基再稼働後の2035年度原子力比率60-70%という野心的な目標を発表した4243。ただし、これは原子力規制委員会の審査合格と防潮堤建設完了が前提条件であり、スケジュール通り進むかは不透明である。
社会的受容性も原子力利用の重要な制約要因である。福島第一原発事故の記憶が残る中、地域住民の理解と合意を得ることは容易ではない。特に、避難計画の実効性、使用済み核燃料の処分、事故時の補償などについて、十分な説明と対策が求められる。
経済性の課題も深刻である。安全対策費の増大により、原子力発電の建設費は大幅に上昇している。一方、再生可能エネルギーのコストは急速に低下しており、新規原子力発電所の経済性は著しく悪化している。既存設備の活用が経済合理性の観点から重要である。
核燃料サイクル政策の見直しも長期的課題である。六ヶ所再処理工場の稼働延期、もんじゅの廃炉、高レベル放射性廃棄物処分場の選定難航など、核燃料サイクルを巡る課題は山積している。これらの課題解決なしには、原子力の持続的活用は困難である。
2035年の原子力発電は、技術的制約、経済的制約、社会的制約の三重の制約の下で、限定的な役割にとどまる可能性が高い。脱炭素化とエネルギー安全保障の両立には、原子力に過度に依存しない、再生可能エネルギーを基軸とした電力システムの構築が現実的な選択となる。
7. 経済影響とコスト評価
7.1 発電コスト比較と競争力分析
2035年の日本における各電源の発電コストは、技術革新と規模拡大により大幅な変化を遂げる。特に再生可能エネルギーのコスト低下は著しく、従来の電源構成を根本的に見直す契機となっている。
太陽光発電コストの低下は最も劇的である。自然エネルギー財団の分析によれば、太陽光発電のLCOE(均等化発電原価)は2030年に5円/kWh程度まで低下し8、これは現在の原子力発電や石炭火力発電よりも安価な水準である。この価格競争力により、太陽光発電は2035年における最も経済的な電源となる。
太陽光発電コストの低下要因として、太陽電池モジュールの変換効率向上、製造技術の改善、設置工法の標準化、運転保守技術の高度化などが挙げられる。特に、ペロブスカイト太陽電池などの次世代技術の実用化により、設置可能場所の拡大と発電効率のさらなる向上が期待される。
風力発電コストも大幅な低下が見込まれる。陸上風力発電は2030年に6.6円/kWh程度8、洋上風力発電は2035年までに8-9円/kWhまで低下する見通しである1112。特に洋上風力発電では、タービンの大型化、浮体式技術の確立、設置・運転保守技術の向上により、欧州並みのコスト水準達成が可能とされている。
蓄電池システムコストの急降下が電力システム全体の経済性を改善する。リチウムイオン電池のコストは2035年に5万円/kWhまで低下し14、これによりエネルギー貯蔵の経済性が飛躍的に向上する。蓄電池システムの導入により、太陽光・風力発電の出力変動対応コストが大幅に削減される。
原子力発電コストは安全対策費の増大により上昇傾向にある。新規制基準対応費用、テロ対策施設建設費、廃炉費用などを考慮すると、新設原子力発電のコストは15円/kWh以上となる見込みである。既設原子炉の再稼働についても、安全対策費と稼働率の低下により、実質的な発電コストは上昇している。
火力発電コストは燃料価格と炭素価格の影響を大きく受ける。石炭火力は燃料費が安価であるものの、CO2排出量が多いため、カーボンプライシングの導入により競争力が大幅に低下する。天然ガス火力は燃料費が高いものの、効率が高くCO2排出量が少ないため、過渡期における競争力を維持する。
学習効果による継続的なコスト低下も重要な要因である。太陽光発電と風力発電では、累積導入量の増加に伴い製造コスト、設置コスト、運転保守コストが継続的に低下する。この学習効果により、2035年以降もさらなるコスト低下が期待される。
系統統合コストを含めた総合的な評価も重要である。変動再生可能エネルギーの大量導入には、送電網強化、調整力確保、予備力確保などの系統統合コストが発生する。しかし、蓄電池技術の進歩と需要側の柔軟性向上により、これらのコストは従来想定より大幅に低減される見込みである。
7.2 化石燃料輸入コスト削減効果
日本の化石燃料輸入依存からの脱却は、エネルギー安全保障の向上と同時に、巨額の経済効果をもたらす。2035年に向けた再生可能エネルギーの大幅拡大により、化石燃料輸入コストの劇的な削減が実現する。
現状の輸入コストは年間約20兆円に達している。原油、天然ガス、石炭の輸入額は、国際価格の変動により大きく左右されるが、ウクライナ情勢以降の価格高騰により、エネルギー輸入が日本の貿易収支に与える影響は深刻化している。
バークレー研究所の分析によれば、2035年にクリーンエネルギー90%のシステムを構築することで、化石燃料(LNGと石炭)の輸入を85%削減することが可能である4。この削減により、年間数兆円規模のコスト削減効果が実現される。
自然エネルギー財団の試算では、電力の80%を自然エネルギーで供給することで、発電用化石燃料費を年間4兆円削減できるとされている221。この削減効果は、再生可能エネルギー設備への投資コストを大幅に上回るため、マクロ経済的には大きな利益となる。
洋上風力発電の効果は特に大きい。Energy Tracker Japanの分析によれば、1GWの洋上風力発電所は8億㎥のガス輸入を代替でき、2022年価格では約9億2,800万ドルのガス輸入コストを削減する効果がある11。政府目標の2030年30GWでは、年間約280億ドル(約4兆円)の輸入コスト削減効果が期待される。
価格変動リスクの軽減も重要な経済効果である。化石燃料価格は地政学的リスクや投機的要因により大幅に変動するため、価格予測が困難である。再生可能エネルギーへの転換により、このような外的要因による価格変動リスクから解放され、長期的なエネルギーコストの安定化が実現される。
エネルギー自給率の向上により、日本のエネルギー安全保障は大幅に改善される。現在約13%のエネルギー自給率は、自然エネルギー財団のシナリオでは2035年に60%まで向上する見込みである24。この自給率向上により、国際情勢の変化に対する日本経済の耐性が大幅に強化される。
雇用創出効果も見逃せない経済メリットである。化石燃料の輸入・流通・発電に従事していた労働者が、再生可能エネルギーの製造・設置・運転保守に転換することで、国内での雇用創出と技術蓄積が進む。特に、洋上風力発電産業では造船、海事工学、電機などの既存産業基盤を活用した新産業創出が期待される。
貿易収支改善効果により、マクロ経済指標の改善も期待される。化石燃料輸入の削減により、日本の貿易収支が改善し、円高圧力の軽減や金利政策の自由度向上などの間接的な経済効果も発生する。
7.3 社会的費用(SOC)を含めた評価
エネルギーシステムの真の経済性を評価するためには、市場価格だけでなく、環境・健康・社会に与える外部費用(社会的費用)を含めた包括的な分析が不可欠である。2035年のエネルギー転換は、これらの社会的費用の大幅な削減をもたらす。
**炭素の社会的費用(SCC: Social Cost of Carbon)**は、CO2排出による気候変動の経済的損失を貨幣価値で評価したものである。米国環境保護庁(EPA)は1トンCO2当たり約200ドル(約3万円)のSCCを採用している。日本の年間CO2排出量約12億トンに適用すると、年間約36兆円の社会的費用が発生していることになる。
バークレー研究所の分析では、炭素の社会的費用を考慮すると、2035年のクリーンエネルギーシステムの発電コストは2020年比で36%低くなるとされている4。これは、CO2削減による気候変動対策費用の節約効果を含めた評価である。
大気汚染による健康影響コストも重要な社会的費用である。化石燃料の燃焼により発生するPM2.5、NOx、SOxなどの大気汚染物質は、呼吸器疾患、循環器疾患、がんなどの健康被害をもたらす。WHO(世界保健機関)の推計では、大気汚染による日本での年間死亡者数は約3万人とされている。
1人当たりの統計的生命価値(VSL: Value of Statistical Life)を約3億円と仮定すると、大気汚染による年間健康被害コストは約9兆円に達する。石炭火力発電の廃止により、このコストの相当部分が削減される。
環境修復コストも考慮すべき要因である。化石燃料の採掘・輸送・利用に伴う環境汚染、生態系破壊、水質汚濁などの環境影響を修復するためのコストは、従来の発電コストに含まれていない。これらの外部費用を内部化すると、化石燃料発電の真のコストは大幅に上昇する。
原子力事故リスクコストも重要な社会的費用である。福島第一原発事故の総コストは20兆円を超えると推計されており、このリスクを発電コストに反映すると、原子力発電の経済性は大幅に悪化する。確率的リスク評価に基づく事故コストの内部化が必要である。
送電網外部性による社会的便益も評価すべきである。分散型再生可能エネルギーの普及により、送電損失の削減、系統信頼性の向上、災害時のレジリエンス強化などの便益が発生する。これらの便益を適切に評価することで、分散型エネルギーシステムの真の価値を把握できる。
雇用・地域経済への影響も社会的費用・便益の重要な要素である。化石燃料産業から再生可能エネルギー産業への転換により、雇用構造と地域経済が変化する。適切な職業訓練と産業転換支援により、この変化を社会的便益に転換することが可能である。
エネルギー安全保障の経済価値を定量化することも重要である。エネルギー自給率の向上により、供給途絶リスクや価格変動リスクが軽減される経済価値は相当なものと推定される。これらのリスク削減効果を適切に評価することで、再生可能エネルギー投資の社会的収益率が明確となる。
社会的費用を含めた包括的な評価により、2035年の再生可能エネルギー中心のエネルギーシステムは、単なる発電コスト以上の大きな社会的・経済的便益をもたらすことが明らかとなる。この便益を適切に政策決定に反映することが、持続可能な社会の実現に不可欠である。
8. 政策提言とロードマップ
8.1 中長期目標設定と制度設計
2035年の電力エネルギー転換を実現するためには、野心的かつ実現可能な中長期目標の設定と、それを支える制度設計の抜本的改革が不可欠である。現在の政策枠組みでは、国際的な気候変動対策要請と技術進歩の速度に対応できない状況にある。
2035年削減目標の設定について、気候変動イニシアティブ(JCI)は日本政府に対して2035年までの温室効果ガス66%以上削減(2019年比)という野心的な目標設定を求めている22。この目標は、IPCC第6次報告書が示す1.5度目標との整合性を確保するために必要な水準である。現在審議会で提示されている2013年度比60%削減(2019年度比53%削減)では国際的な要請に応えられない23。
電力部門の脱炭素化目標として、複数の研究機関が以下の目標を提案している:
これらの目標の中では、自然エネルギー財団とバークレー研究所の提案が科学的根拠と技術的実現可能性に基づいており、2035年の中間目標として適切である。
FIT/FIP制度の発展的改革が必要である。現在の固定価格買取制度(FIT)から市場連動型のプレミアム制度(FIP)への移行は進んでいるが、2035年に向けてはさらなる制度改革が求められる。具体的には、長期契約による投資予見性の確保、系統サービス提供への適切な対価、需給調整市場への参加促進などが重要である。
カーボンプライシングの本格導入は、脱炭素投資の経済性確保のために不可欠である。現在のGX-ETS(自主参加型排出量取引制度)は2033年度から義務化される予定だが、炭素価格は1,500円/t-CO2と国際水準(5,000-10,000円/t-CO2)と比較して低すぎる8。実効性のあるカーボンプライシングにより、化石燃料と再生可能エネルギーの競争条件を適正化する必要がある。
容量市場制度の見直しも重要である。現在の容量市場は既存火力発電への過度な優遇となっており、再生可能エネルギーと蓄電池の競争を阻害している。将来の電力システムに適合した容量価値の評価方法、蓄電池やデマンドレスポンスの適切な評価、脱炭素電源への優遇措置などの制度改革が必要である。
送電網整備の計画的推進のため、広域系統整備計画の抜本的見直しが求められる。現在の計画は再生可能エネルギーの大量導入に対応できておらず、北海道と本州間の連系線強化、洋上風力開発に対応した海底ケーブル整備、配電網のスマート化などを前倒しで実施する必要がある。
8.2 規制改革・土地利用・合意形成の加速
2035年までの限られた時間で大規模な再生可能エネルギー導入を実現するためには、現在の規制・制度が抱える構造的な課題を抜本的に解決する必要がある。特に、環境アセスメント手続きの長期化、土地利用規制の複雑さ、地域合意形成の困難さが最大のボトルネックとなっている。
環境アセスメント手続きの迅速化は最優先課題である。現在、風力発電の環境アセスメントには3-4年を要しているが、政府は手続き期間の半減を目標としている2。具体的な改革措置として、以下の施策が必要である:
アセスメント手続きの並行実施により、従来の逐次手続きから同時並行手続きへの転換を図る。事業者による自主的な環境調査と法定アセスメントの重複排除、関係機関協議の効率化、デジタル技術を活用した手続きの自動化などにより、大幅な期間短縮が可能である。
新築建築物への太陽光発電設置義務化の全国展開を推進する。東京都が2025年4月から開始する制度を参考に、全国の自治体での同様の制度導入を促進する。国レベルでの制度化も検討し、建築基準法や省エネルギー法の改正により、新築住宅・建築物への太陽光発電設置を原則義務化する。
洋上風力のセントラル方式の本格導入により、開発リスクの低減と事業化の加速を図る。政府が海域選定、風況・地質調査、環境アセスメント、漁業調整を事前に実施し、民間事業者は発電事業に専念できる体制を構築する37。欧州で実績のある手法であり、日本でも早急な制度化が必要である。
農地での太陽光発電導入促進のため、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の規制緩和を進める。農地転用許可手続きの簡素化、一時転用期間の延長、営農継続要件の柔軟化などにより、農業経営と再生可能エネルギー導入の両立を図る。
地域共生型開発の制度化により、地域住民の理解と協力を確保する。再生可能エネルギー事業による地域経済効果の最大化、環境保全措置の徹底、住民参加型事業スキームの導入などにより、地域と事業者の共栄関係を構築する。
土地利用規制の見直しも重要である。国立・国定公園、森林法、農地法、都市計画法などの各種規制により、再生可能エネルギー開発が制約される場合が多い。環境保全との両立を前提としつつ、過度に厳格な規制の緩和や手続きの合理化を進める。
地方自治体の権限強化により、地域主導の再生可能エネルギー開発を促進する。再生可能エネルギー促進区域の設定権限、事業者選定への関与、地域貢献要求権などを自治体に付与し、地域の実情に応じた柔軟な制度運用を可能とする。
8.3 地方自治体・企業の役割と支援策
2035年のエネルギー転換は、国の政策だけでは実現できない。地方自治体と企業が主体的に取り組み、相互に連携することで初めて達成可能となる。そのためには、各主体の役割の明確化と効果的な支援策の提供が不可欠である。
地方自治体の役割拡大について、自然エネルギー財団は「自治体の最も根源的な責務は住民の安全、生命、財産を守ること」であり、気候変動対策はこの責務の中核であると位置づけている8。具体的には、以下の役割が期待される:
地域エネルギー計画の策定により、地域の再生可能エネルギーポテンシャルを最大限活用する計画を立案する。地域の気象条件、土地利用状況、電力需要パターンなどを詳細に分析し、最適な電源構成と導入スケジュールを設定する。
東京都の先進事例は全国の自治体にとって重要な参考となる。2035年までに都内に太陽光発電設備350万kW設置という野心的な目標設定34、新築住宅への太陽光発電設置義務化、次世代型太陽電池の普及促進など、包括的な政策パッケージを展開している。
川崎市も新築住宅への太陽光発電設置義務化を導入しており8、大都市部での屋根置き太陽光発電普及の有効な手法として注目される。これらの先進事例の全国展開により、屋根置き太陽光発電の大幅拡大が期待される。
**企業のPPA(電力購入契約)**活用促進が重要である。RE100加盟企業を中心に、再生可能エネルギー電力の長期購入契約への関心が高まっている。しかし、日本では追加性のある再生可能エネルギー電力の供給不足により、企業の調達需要に応えられていない状況がある8。
コーポレートPPAの普及拡大のため、以下の支援策が必要である:
- PPA契約に対する税制優遇措置の導入
- 再生可能エネルギー電力の環境価値認証制度の整備
- 企業の再生可能エネルギー調達目標設定への支援
- 中小企業向けの集合型PPA制度の創設
**日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)**などの企業グループによる自主的な取り組みも重要である。2035年石炭火力廃止を求める企業グループの活動22は、産業界からの政策転換要求として大きな意味を持つ。
地方自治体への支援強化も不可欠である。財政基盤の強化、専門人材の確保、技術的支援の提供などにより、自治体の実行力向上を図る必要がある。特に、小規模自治体では再生可能エネルギー事業の専門知識や経験が不足しているため、国や都道府県による技術支援体制の整備が重要である。
地域新電力の育成も地域主導のエネルギー転換には不可欠である。地域の再生可能エネルギーを地域で消費する「地産地消」のエネルギーシステム構築により、エネルギー代金の地域外流出を防ぎ、地域経済の循環を強化できる。
金融機関の役割も重要である。地域金融機関による再生可能エネルギー事業への融資拡大、グリーンボンドの発行促進、ESG投資の拡大などにより、民間資金の積極的な活用を図る。特に、地域密着型の事業には地域金融機関の支援が不可欠である。
産業集積の形成により、再生可能エネルギー関連産業の競争力強化を図る。太陽光発電、風力発電、蓄電池などの製造業、設置・保守サービス業、エンジニアリング業などの集積により、コスト削減と技術革新を促進する。特に、洋上風力発電産業では港湾インフラの整備と関連産業の集積が成功の鍵となる。
これらの多面的な取り組みにより、2035年の日本は官民連携による世界最先端のエネルギー転換を実現し、持続可能な社会の模範を国際社会に示すことができる。
9. 結論と今後の展望
9.1 2035年エネルギー転換の実現可能性
本レポートの包括的な分析により、2035年の日本における電力エネルギーの大幅な脱炭素化は、技術的にも経済的にも実現可能であることが明らかとなった。複数の独立した研究機関による詳細なシミュレーション結果は、いずれも高い再生可能エネルギー比率での電力安定供給が可能であることを示している。
技術的実現可能性について、自然エネルギー財団の分析では2035年に自然エネルギー80%224、バークレー研究所の研究では同90%(再エネ70%、原子力20%)34の電力システム構築が可能とされている。これらの分析では、太陽光発電280GW、風力発電60GW、蓄電池72GW/184GWhという具体的な設備容量が示されており、現在の技術延長線上で達成可能な水準である。
経済的実現可能性も確認された。太陽光発電コストの5円/kWh、風力発電コストの6-9円/kWhへの低下により8、再生可能エネルギーは既存の火力発電や原子力発電よりも安価な電源となる。化石燃料輸入の85%削減により年間数兆円のコスト削減効果4があり、これは再生可能エネルギー設備への投資コストを大幅に上回る。
系統安定性の確保についても、蓄電池技術の進歩と送電網の強化により対応可能であることが示された。特に、V2G技術の活用により、EV1,000万台の蓄電容量(約100GWh)を系統安定化に活用できれば3、固定式蓄電池の導入コストを大幅に削減できる。
国際比較の観点からも、日本の2035年目標は適切な水準である。欧州各国は2030-2035年の石炭火力完全廃止を既に決定しており16、中国も2060年カーボンニュートラルに向けて再生可能エネルギーの急速な拡大を進めている。日本が国際競争力を維持するためには、これらの国際動向に適合した野心的な目標設定が不可欠である。
9.2 残された課題と解決策
2035年エネルギー転換の実現には、技術的・制度的・社会的な課題が依然として存在する。これらの課題を克服するための具体的な解決策の実行が、目標達成の成否を決定する。
規制・制度改革の遅れが最大の課題である。環境アセスメント手続きの長期化、土地利用規制の複雑さ、系統連系手続きの煩雑さなどにより、再生可能エネルギーの導入速度が制約されている。解決策として、アセスメント手続きの並行実施、デジタル技術を活用した手続き効率化、一元的な窓口設置などの抜本的な制度改革が必要である。
送電網整備の遅れも深刻な課題である。現在の広域系統整備計画では、2035年の再生可能エネルギー大量導入に対応できない。特に、北海道と本州間の連系線強化、洋上風力に対応した海底ケーブル整備の前倒し実施が急務である。送電網整備には5-10年の期間を要するため、2025年中の着工が必要である。
人材不足も深刻化している。再生可能エネルギーの設計・施工・運転保守に従事する技術者、系統運用の専門家、プロジェクトマネージャーなどの人材が大幅に不足している。解決策として、大学・高専での専門教育強化、企業での実務研修拡充、海外からの技術者受け入れなどの包括的な人材育成策が必要である。
社会受容性の課題も看過できない。大規模な再生可能エネルギー開発に対する地域住民の懸念、景観や環境への影響に対する不安、既得権益との調整などが障害となる場合がある。解決策として、地域共生型開発の制度化、住民参加型事業スキームの普及、適切な利益還元メカニズムの構築が重要である。
技術的課題では、蓄電池の大量導入に伴うリサイクル体制の整備、系統の慣性力確保、サイバーセキュリティ対策などが新たな課題として浮上している。これらの課題に対しては、産学官連携による技術開発の加速、国際標準の策定への積極的参加、実証事業による経験蓄積が必要である。
9.3 2050年カーボンニュートラルへの道筋
2035年のエネルギー転換は、2050年カーボンニュートラル実現への重要な中間段階として位置づけられる。2035年の成果を基盤として、2050年に向けてはさらなる技術革新と社会システムの変革が必要となる。
電力部門の完全脱炭素化は2040年代前半には達成される見込みである。2035年時点で再生可能エネルギー80-90%を実現すれば、残る10-20%の脱炭素化は水素発電、アンモニア発電、CCS付き火力発電などにより対応可能である。特に、余剰再生可能エネルギーを活用したグリーン水素製造により、電力貯蔵と調整電源の両方の機能を担うことができる。
産業部門の脱炭素化は2035年以降の重要課題となる。鉄鋼業の水素還元製鉄、化学工業の電化・水素化、セメント産業のCCS導入などにより、製造業の脱炭素化を段階的に進める。これらの産業転換には相当規模の電力需要増加が伴うため、2040年代には現在を上回る電力需要となる可能性がある。
運輸部門の脱炭素化は2030年代に大きく進展し、2040年代には概ね完了する見込みである。乗用車のEV化、商用車の電動化・水素化、海運・航空の代替燃料利用などにより、運輸部門からのCO2排出は大幅に削減される。
熱需要の脱炭素化は最も困難な課題の一つである。家庭・業務部門の暖房・給湯の電化、産業部門の工業炉の電化・水素化、地域熱供給システムの再生可能エネルギー化などにより、段階的な脱炭素化を進める。
国際協力の重要性も増している。アジア地域でのエネルギー転換支援、水素・アンモニアの国際サプライチェーン構築、脱炭素技術の輸出促進などにより、日本の脱炭素化と国際貢献を同時に実現する。特に、日本が得意とする高効率機器、制御技術、システム統合技術の海外展開により、地球規模でのCO2削減に貢献できる。
循環経済との統合も2050年に向けた重要な要素である。廃棄物のエネルギー利用、リサイクル材料の活用、製品の長寿命化などにより、資源効率性とエネルギー効率性を同時に向上させる。特に、蓄電池、太陽光パネル、風力タービンなどの大量廃棄に対応するリサイクル産業の構築が急務である。
2035年日本の電力エネルギー転換は、技術革新と制度改革、そして社会全体の意識変革により実現可能である。この転換により、日本はエネルギー安全保障の確保、経済競争力の向上、地球環境の保全を同時に達成し、持続可能な社会の実現に向けた確実な一歩を踏み出すことができる。残された時間は限られているが、全ての関係者が連携して取り組めば、この歴史的な転換を成功させることは十分可能である。
- https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20240619.php
- https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20230411.php
- https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/030301233/
- https://beyond-coal.jp/documents/berkeleylab-report-2023/
- https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/S1-JPEA_TMasukawa_20240314.pdf
- https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/conference/energy/20240322/240322energy03.pdf
- https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20240904_rooftop.php
- https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/240117_TriplingRE_TAikawa.pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/green_power/pdf/008_04_00.pdf
- https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001464918.pdf
- https://www.energytracker.jp/20230612_renewable_offshore-wind-in-japan-the-untapped-potential/
- https://wa.city.noshiro.lg.jp/wind/455/
- https://eins-ltd.com/column/2025%E5%B9%B4%E7%89%88%EF%BD%9C%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%94%A8%E8%93%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%81%A8%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%8B%95%E5%90%91/
- https://www.enegaeru.com/electricityfuturesmarket
- https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/05_jidosha.html
- https://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20240516_e01/
- https://u-power.jp/sdgs/future/000670.html
- https://econews.jp/column/13982/
- https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20250321.php
- https://japanclimate.org/wp/wp-content/uploads/2024/07/JCI-message-2035ndc-attachment1_JP.pdf
- https://beyond-coal.jp/documents/report/renewable-ei_energy-report-2023/
- https://beyond-coal.jp/news/jci_message-to-2035/
- https://www.jcp.or.jp/web_policy/2024/12/post-999.html
- https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_2035study_2406.pdf
- https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/
- https://solarjournal.jp/policy/57241/
- https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/blog/article_101.html
- https://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/24121101.html
- https://www.iti.or.jp/kikan112/112sasai.pdf
- https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/09/medium_2309_01.pdf
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/52/3/52_841/_article/-char/ja/
- https://prtimes.jp/magazine/2035-problem/
- https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/01940/
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/perovskite
- https://www.rts-pv.com/news/202310_14393/
- https://go100re.jp/3572
- https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_OSWcentral.pdf
- https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/S1-REI_SKimura_20240314.pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/006_06_00.pdf
- https://www.jera.co.jp/system/files/private/%E6%B7%BB%E4%BB%98%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%9A2035%E5%B9%B4%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
- https://japanclimate.org/wp/wp-content/uploads/2022/07/JCI-webinar0708_REI-YO_web2.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=6HpH8SiBoJg
- https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20250326/7000074321.html
- https://www.semanticscholar.org/paper/e81af24c5fc73f77bd60db310bfa37377d0f5faf
- https://www.semanticscholar.org/paper/c48f650b3ba3e693e9aecadec7fbfc2adf76d9ce
- https://www.semanticscholar.org/paper/b36f7c4119884760e64dadb78e64c53716cb942d
- https://www.semanticscholar.org/paper/7b2aac0a7be098d01f09ac32e94f21991724b94f
- https://www.semanticscholar.org/paper/d8e25d19ab1b934b2954c2399635d3d3cf69b0db
- https://www.semanticscholar.org/paper/bc6889341d05154ac8f490c2b277a468c7323cd2
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/bplus/6/2/6_126/_article/-char/ja/
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspe/86/1/86_13/_article/-char/ja/
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/069_03_00.pdf
- https://japan-clp.jp/archives/16288
- https://www.occto.or.jp/iinkai/shorai_jukyu/2023/files/shoraijukyu_03_02_01.pdf
- https://www.wwf.or.jp/activities/data/20240531climate03.pdf
- https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20241128.php
- https://www.nef.or.jp/topics/2025/20250530.html
- https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/lbnl_2035_japan_report_japanese_publish.pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/074_01_00.pdf
- https://www.jaif.or.jp/information/ai_energy
- https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_2035_Study_JP.pdf
- https://arxiv.org/pdf/2109.08363.pdf
- https://www.mdpi.com/2071-1050/6/4/2087/pdf?version=1424778123
- https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5370/pdf
- https://www.mdpi.com/2071-1050/14/24/17005/pdf?version=1671531222
- http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=77212
- http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=47095
- https://arxiv.org/abs/2105.03562
- https://arxiv.org/pdf/2502.04205.pdf
- https://www.nedo.go.jp/content/100960323.pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/064_01_00.pdf
- https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/14038/
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/028_05_00.pdf
- http://arxiv.org/pdf/2308.12984.pdf
- https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLIV-3-W1-2020/37/2020/isprs-archives-XLIV-3-W1-2020-37-2020.pdf
- http://downloads.hindawi.com/journals/jen/2017/4107614.pdf
- https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/download/5535/5535
- https://arxiv.org/pdf/2205.11944.pdf
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10686099/
- https://climateintegrate.org/wp-content/uploads/2023/02/Shiraishi_JP_Final_Report_Briefing_Slides_20230227edit.pdf
- https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/055/055_004.pdf
- https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2024/pdf/1_2.pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/074_10_00.pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/044_01_00.pdf
- https://cnic.jp/59835
- https://www.env.go.jp/council/content/i_05/000070309.pdf
- https://www.semanticscholar.org/paper/e64e64d0679e5b1a59523957662e8a9bb92c249a
- https://www.semanticscholar.org/paper/2370fc628785791f7b14a3bc8be748eb0cc1d696
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10276234/
- https://www.mdpi.com/2071-1050/8/1/52/pdf?version=1452177822
- https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/5931/pdf
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10440442/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11372380/
- https://www.enegaeru.com/2025-2030kounetsuhi
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/067_01_00.pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/chikudenchi_sustainability/pdf/001_s01_00.pdf
- https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2024/data/05_05.pdf
- https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241227006/20241227006-7.pdf
- https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/yojo_taiyoko_chinetsu.pdf
- https://emira-t.jp/pedia/18258/
- https://www.adb.org/sites/default/files/publication/897406/adbi-wp1403.pdf
- https://www.adb.org/sites/default/files/publication/897356/adbi-wp1401.pdf
- https://arxiv.org/pdf/2310.05811.pdf
- https://arxiv.org/pdf/2207.07969.pdf
- http://thesai.org/Downloads/Volume3No7/Paper_6-The_Japanese_Smart_Grid_Initiatives,_Investments,_and_Collaborations.pdf
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11795043/
- https://www.nikkei.com/nkd/fund/?fcode=03311159
- https://www.renewable-ei.org/activities/projects/energymix.php
- https://www.tfu.ac.jp/volunt/arpn890000001uiv-att/s9n3gg0000000p5z.pdf
- https://ynu.repo.nii.ac.jp/record/12146/files/YJSS27-1-4-Ohama.pdf
- https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2023/053/053_004.pdf
- https://www.mext.go.jp/content/20250314_mxt_kyoikujinzai01-000041145_35.pdf
- https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html
- https://japanclimate.org/news-topics/jci-message-2035ndc-release/
- https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/281381.pdf
- https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/blog/article_115.html
- https://green-recovery-japan.org
- https://www.semanticscholar.org/paper/720d5db83d79a4b7eb3c1591ad79709ac00dc157
- https://www.semanticscholar.org/paper/883736a690a728eac87c045a2c7e18cce00b8dc7
- https://www.semanticscholar.org/paper/8c5651d52ff4215b71d39e0ae0b680c1b77f00bd
- https://www.semanticscholar.org/paper/6ab137ad024fd257dd4cd663d13787a3fd1dee93
- https://www.semanticscholar.org/paper/af96d8cc467d54792f32ff52ccb5217f93cef7a6
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/56/3/56_1275/_article/-char/ja/
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/hgs/95/1/95_1/_article/-char/ja/
- https://www.semanticscholar.org/paper/62305587ddc42f94354800266b66d6c4dc2b18e0
- https://www.dir.co.jp/report/research/economics/outlook/20250522_025104.pdf
- https://seikatsusoken.jp/futuretimeline/search_category.php?year=2035&category=6
- https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/shisan/r7chuuchouki1.pdf
- https://evdays.tepco.co.jp/entry/2021/09/28/000020
- https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000152713.pdf
- https://revitalizejapan.com/research/research-1109/
- https://www.soumu.go.jp/main_content/000273900.pdf
- https://www.mlit.go.jp/common/001378244.pdf
- https://www.nttev.com/column/2035_ban_new_gasoline_vehicle_sales/
- https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2035/
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/aije/77/677/77_583/_article/-char/ja/
- http://www.jstage.jst.go.jp/article/jiep1998/10/4/10_4_262/_article/-char/ja/
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/hrl/3/0/3_0_14/_pdf
- https://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/469/pdf
- https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-environ-112321-091140
- https://www.mdpi.com/1996-1073/13/19/5153/pdf
- https://www.mdpi.com/2073-4433/10/5/265/pdf?version=1557733394
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8679570/
- https://www.erm.com/ja/insights/20302035/
- https://www.mdpi.com/2071-1050/15/2/1418/pdf?version=1673927252
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7859221/
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/ese3.233
- http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=85331
- https://www.epj-pv.org/articles/epjpv/pdf/2021/01/pv210010.pdf
- https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0144598720979256
- https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7680/pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/073_01_00.pdf
- https://www.nedo.go.jp/content/100889993.pdf
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/021_03_00.pdf
- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0122J0R00C24A5000000/
- https://ejournal.pnc.ac.id/index.php/infotekmesin/article/view/442
- https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/10836/pdf?version=1632919778
- https://www.mdpi.com/1996-1073/17/11/2687/pdf?version=1717226059
- http://downloads.hindawi.com/journals/jen/2017/4865913.pdf
- https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/ninteikeikaku/download/38-10.pdf
- https://shizenenergy.net/decarbonization_support/column_seminar/seventh_strategic_energy_plan/
- https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/048_00_05.pdf
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/sposun/27/1/27_1_61/_article
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejppce/67/1/67_1_108/_article/-char/ja/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7406701/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11301048/
- http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90002831.pdf
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/tgis.12525
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5136603/
- https://namvd.editorum.ru/en/storage/download/40162
- https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1505/pdf?version=1552461335
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7944044/
- https://arxiv.org/pdf/2204.00198.pdf
- http://ijps.accscience.com/index.php/IJPS/article/view/301
- https://www.smbc.co.jp/hojin/report/resources/pdf/1_00_CRSDOutlook.pdf?version=250409
- https://www.shindengen.co.jp/column/vol13/
- https://www.co-medical.com/knowledge/article880/
- https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2022/pdf/01-03-01.pdf
※本ページは、AIの活用や研究に関連する原理・機器・デバイスについて学ぶために、個人的に整理・記述しているものです。内容には誤りや見落としが含まれている可能性もありますので、もしお気づきの点やご助言等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※本ページの内容は、個人的な学習および情報整理を目的として提供しているものであり、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証も行いません。本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことによって発生した損害(直接的・間接的・特別・偶発的・結果的損害を含みますが、これらに限りません)について、当方は一切責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の責任でお願いいたします。