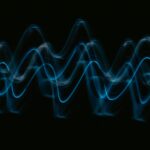6. 故障予知のアプローチ
6.3 異常検知(クラスタリング型手法)
異常検知のクラスタリング型手法は、「似たもの同士は近くに集まる」という直感に基づき、データをいくつかのまとまり(クラスタ)に分け、そのまとまりから外れた点や、極端に小さなまとまりに属する点を「異常の疑い」とみなす考え方である。多次元データ(例えば振動・温度・電流を同時に扱う)でも適用しやすく、正常運転が自然に作る“集まり”からの逸脱を検出できるのが特長である。[1][2][3][4]
クラスタリングで異常を見つける基本は二通りある。1) クラスタに属さない(分類できない)点を異常とみなす、2) どのクラスタにも属するが中心から遠い(周囲と違いすぎる)点を異常とみなす、の二つである。前者は密度に基づく手法が得意で、後者は距離に基づく手法がわかりやすい。[2]
代表的なアルゴリズムの使い分けを紹介する。k-means(k平均法)は、データの中心(重心)をk個仮定し、各点を最も近い中心に割り当て、中心を更新する処理を繰り返す手法で、計算が速く実務で広く使われる。クラスタリング後は「中心からの距離」を異常度として使えば、同じクラスタでも“中心から外れた点”を検出できる。実務では、クラスタ分け自体で少数しか含まないグループが見つかれば、そのグループを“異常候補”として扱うこともある。[5][6][7][8][2]
密度ベースのDBSCANは、近くに十分な点が集まる“密な領域”をクラスタとみなし、そこから外れた点を「ノイズ」として自動的に識別する性質があり、どのクラスタにも属しにくい孤立点を異常として扱いやすい。また、丸い形に限らず、不規則な形のクラスタにも適応できるため、現実的な複雑データでも使いやすい利点がある。さらに、DBSCANは事前にクラスタ数を決める必要がないため、kの選定が難しい現場でも導入しやすい。[9][10][11][12]
クラスタリングと異常度の設計には、いくつかの定番アプローチがある。- 距離に基づく異常度: k-meansで得た各クラスタ中心への距離を異常度とする(遠いほど異常らしい)。- 小クラスタ重視: クラスタサイズが極端に小さい場合、そのクラスタ所属点の異常度を高くみなす(XBOSのような考えに近い)。- 密度に基づく判定: DBSCANでノイズ扱いになった点を異常候補にする。これらは互いに補完的で、用途に応じて併用できる。[11][8][12][13][2]
実務の手順は次の通りである。1) 特徴量を準備(RMS、バンドエネルギー、ピーク数、スペクトル重心など)し、スケールをそろえる(標準化や正規化)。2) 可視化や主成分分析で大まかな分布を把握する(次元圧縮で散布図の直感を得る)。3) k-meansやDBSCANを試し、クラスタのまとまり方を確認する(k-meansはkの候補を変えて比較、DBSCANはeps・min_samplesを探索)。4) 異常度の指標を決める(中心距離、クラスタサイズ、ノイズ判定など)。5) 閾値を検証データで調整し、過剰検知と見逃しのバランスを取る(PRやROCを参考)。6) 本番適用後も分布の変化(データ漂移)を監視し、パラメータや基準の見直しを定期的に行う。[14][15][8][12][13][16][2][5]
k-meansを使う場合の勘どころとして、クラスタ数kの選定がある。肘(エルボー)法などで“まとまり感”を見て候補を絞り、異常検知の観点(中心からの距離分布が識別に役立つか)で最終決定するとよい。また、k-meansは球状のクラスタを仮定する性質があるため、形がいびつな分布ではDBSCAN等への切り替えを検討する。DBSCANはパラメータ(近傍半径eps、最低点数min_samples)で結果が変わるので、k距離プロットでepsの目安を取りつつ、過剰なノイズ判定にならない設定を探るのが実務的である。[10][8][12][5][9]
クラスタリング型の利点は、- ラベルがなくても導入でき、未知のパターンにも対応しやすい(探索がしやすい)。- 多次元データの“まとまり”を自然に捉え、少数派や孤立点の発見に向く。一方で注意点は、- スケールや距離尺度に結果が左右されるため、前処理(標準化)が必須である。- クラスタ形状の仮定やパラメータ選定に感度があり、データが変わると再調整が必要になる。- 異常理由の説明には、可視化や特徴寄与の確認など追加の解釈工程が必要になる。[17][3][15][12][2][9]
実例イメージを挙げる。- ディスクの健全性データ(SMART指標)を3次元にまとめ、k-meansで2クラスタに分けたところ、一部のモデルが少数クラスタ側に単独で分類され、異常候補として検知できた。- 同じクラスタ内でも中心からの距離が大きい個体をアラート対象にするルールで、きめ細かな監視を運用できた。- DBSCANで製造ラインの多次元ログをクラスタリングした際、どのクラスタにも属さない点群(ノイズ)が稀に現れ、それらを優先点検対象の異常候補として抽出できた。[12][2][11]
関連手法として、クラスタリングと距離尺度の組み合わせや、クラスタリング後の距離分布にマハラノビス距離を用いる改良も知られており、クラスタごとの形と分散に合わせて「どれだけ外れているか」を測る工夫が有効である。また、BirchやX-meansといった発展手法も実装上の選択肢になりうる。[18][15][2]
導入のチェックリストをまとめる。- 特徴量は意味が通るものを選び、スケールを必ず合わせる。- k-meansとDBSCANを最低限比較し、データ形状に合う方を選ぶ。- 異常度の定義(中心距離・サイズ・ノイズ)を明文化し、閾値は検証で調整する。- 結果の可視化(散布図、中心と距離、ノイズ点の表示)で現場説明に耐える形にする。- データ分布が変わる前提で、定期的な再学習・再推定の計画を持つ。[15][8][13][16][2][5][9][12]
クラスタリング型手法は、ラベルが乏しい現場でも「いつもと違う」を定量化し、少数派や孤立点を抽出する実用的な枠組みである。距離ベースのk-means、密度ベースのDBSCANを出発点に、データの形と目的に合わせて異常度の指標と閾値を設計すれば、故障予知の初期スクリーニングとして高い有効性を発揮できる。[8][2][12] [1] https://mdsc.kyushu-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2023/07/37ee1bbe36c38c9884cf04d874aa5396.pdf
[2] https://www.splunk.com/ja_jp/blog/platform/4-way-detection-by-machine-learning-part2.html [3] https://media.emuniinc.jp/2025/01/20/abnormal-value-detection/ [4] https://www.skillupai.com/blog/tech/about-anomaly-detection/ [5] https://iot.kyoto/iotan_blog/2023/06/06/14055/ [6] https://nuco.co.jp/blog/article/0vGgGgOf [7] https://deus-ex-machina-ism.com/?p=54834 [8] https://learn.microsoft.com/ja-jp/archive/msdn-magazine/2013/february/data-clustering-detecting-abnormal-data-using-k-means-clustering [9] https://jp.linkedin.com/pulse/%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84ai%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86-ai-glossary-vector-holdings-vector-holdings-wvy4c [10] https://mqlinvestmentlab.com/aboutaboutdbscanclustering/ [11] https://it.webcli.jp/topics/dbscan/ [12] https://wakame-msds.com/dbscan/ [13] https://www.scutum.jp/information/waf_tech_blog/2018/03/waf-blog-054.html [14] https://datamix.co.jp/media/datascience/what-is-clustering/ [15] https://www.chowagiken.co.jp/blog/anomalydetection_introduction [16] https://tech.dentsusoken.com/entry/2024/06/24/k-means%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%A8%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96 [17] https://www.geolab.jp/documents/column/ai-005/ [18] https://note.com/e_dao/n/n1f2fdfef278f [19] https://exawizards.com/column/article/ai/clustering/ [20] https://innovative.jp/archives/670※本ページは、AIの活用や研究に関連する原理・機器・デバイスについて学ぶために、個人的に整理・記述しているものです。内容には誤りや見落としが含まれている可能性もありますので、もしお気づきの点やご助言等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※本ページの内容は、個人的な学習および情報整理を目的として提供しているものであり、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証も行いません。本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことによって発生した損害(直接的・間接的・特別・偶発的・結果的損害を含みますが、これらに限りません)について、当方は一切責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の責任でお願いいたします。