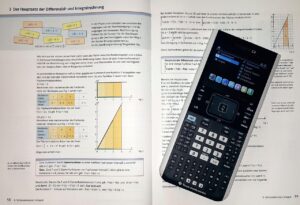1. 序論・背景
パルス圧縮は、送信パルスに時間内変調(位相や周波数の符号化)を施し、受信側で整合フィルタ(matched filter)や相互相関処理を行って、長いパルスのエネルギー利得と短いパルスの距離分解能を同時に実現する信号処理手法である。長い送信パルスは平均送信電力や受信SNRの向上に有利だが、通常はパルス幅が広いほど距離分解能が悪化するため、変調と整合フィルタで圧縮して短い有効パルスに戻すのがパルス圧縮の基本的な考え方である。この手法は、レーダー、ソナー、超音波、さらにはリモートセンシングや気象観測など多様な分野で応用されている。dsp-book.narod+3
パルスレーダの基本では、矩形の無変調パルス幅τの距離分解能はおよそcτ/2(cは伝搬速度)に制約されるため、高い距離分解能を得るには短パルスが必要になる。しかし短パルスはパルスエネルギーを減らしSNRを悪化させるため、探知距離や検出性能が低下しがちである。パルス圧縮は、長パルスに広帯域の符号化を施し、受信で整合フィルタにより時間的に圧縮することで、等価的に「短い有効パルス幅」(高分解能)と「長い送信時間に基づく大きなエネルギー」(高SNR)を両立させる。この際に重要となる評価概念が曖昧さ関数(ambiguity function)で、時間遅延とドップラーの2次元で波形の性質と整合フィルタ出力を表し、分解能やドップラー耐性、サイドローブ特性を統一的に示す。wikipedia+4
本レポートでは、パルス圧縮の原理、波形方式、整合フィルタ設計、サイドローブ低減、システム設計指標、応用事例、実験・シミュレーション、最新動向と課題を、初学者にも理解できるよう専門用語を説明しながら、ビジネス活用を意識して体系的に整理する。mathworks+2
※本ページは、AIの活用や研究に関連する原理・機器・デバイスについて学ぶために、個人的に整理・記述しているものです。内容には誤りや見落としが含まれている可能性もありますので、もしお気づきの点やご助言等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※本ページの内容は、個人的な学習および情報整理を目的として提供しているものであり、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証も行いません。本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことによって発生した損害(直接的・間接的・特別・偶発的・結果的損害を含みますが、これらに限りません)について、当方は一切責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の責任でお願いいたします。
2. パルス圧縮の基本原理
パルス圧縮は「パルス内変調」と「整合フィルタ」によって実現される。パルス内変調とは、送信パルスの中で位相や周波数を時間的に変化させること(例:バーカー符号の位相反転、線形FMによるチャープ)で、受信では送信波形に一致するインパルス応答を持つ整合フィルタで相互相関を取り、出力が狭い主ローブ(圧縮パルス)となるようにする。整合フィルタは、AWGN下で出力SNRを最大化する最適フィルタであり、入力波形に時間反転・複素共役を施した応答を持つ。udrc.eng.ed+2
圧縮率は一般に時間帯域積TB(パルス持続時間Tと有効帯域幅Bの積)で特徴づけられ、整合フィルタ後の有効パルス幅はおおむね1/Bに比例して狭まるため、圧縮率は約TBとなる。距離分解能は約c/(2B)で与えられるため、広帯域化が分解能改善に直結する。曖昧さ関数は、波形の時間遅延τとドップラーfに対する整合フィルタ出力の大きさを示す2次元関数で、ゼロドップラーカットは自己相関、ゼロディレイカットはスペクトル包絡に対応し、主ローブ幅(分解能)とサイドローブレベル(誤検出・マスキングリスク)を評価する。dsp-book.narod+3
サイドローブとは、主ローブ周囲に現れる小ピークで、近接する強目標の側波帯で弱目標が埋もれる「マスキング」リスクをもたらすため、ピークサイドローブレベル(PSL)や積分サイドローブレベル(ISL)で管理される。波形設計やフィルタ重み付けでPSL/ISLを低減する一方、主ローブ幅の広がり(分解能低下)やSNR損失とのトレードオフが生じる。eit.lth+3
3. パルス圧縮方式の分類
位相符号化方式は、パルス内で位相を±1(2値)あるいは多相に切り替える方式で、代表例がバーカー符号やM系列、最小PSL/ISLを狙う最適化長符号である。バーカー符号は短長のみ実在が知られ、長さ13が最大で、自己相関のサイドローブが±1に抑えられる特長があるが、長符号が存在しない制約がある。M系列は擬似雑音系列で良好な統計性を持つがPSLはバーカーに劣ることが多く、長符号最適化(MPS: Minimum Peak Sidelobe など)や多相最適化でPSL/ISLを改善できる。norbertwiener.umd+4
チャープ(線形FM: LFM)方式は、パルス内で周波数を直線的に掃引する波形で、実装容易性とドップラー耐性のバランスが優れるため広く用いられる。LFMはゼロドップラーで狭い時間主ローブを得つつ、ドップラーが小さい範囲では圧縮出力の劣化が小さい「ドップラー許容性」を持つことが経験的・理論的に知られている。非線形FM(NLFM)はサイドローブ低減のため掃引法則を最適化するが、ドップラーに敏感になりやすい点が課題で、用途に応じたトレードが必要である。その他、複合符号やコステロ型など、PSL/ISLやドップラー耐性の両立を狙う多様な設計が研究されている。wikipedia+5
4. 整合フィルタ設計と実装
整合フィルタは、入力波形の時間反転・複素共役をインパルス応答に持つフィルタで、アナログ実装(表面弾性波SAW素子など)とデジタル実装(FIR, FFTベース相関器)がある。デジタル実装ではFIRベースのタップ係数として送信波形の共役時間反転を用いればよく、ウィナー型(雑音・干渉を考慮した)フィルタ化や窓関数適用でサイドローブ低減を図ることができる。窓関数や重み付け(TaylorやKaiserなど)によりPSL/ISLを下げられる一方、主ローブ幅の増加(分解能低下)や若干のSNR損失が生じるため、検出要件に合わせた最適化が必要となる。its.ntia+5
実機実装では、送受信同期(トリガ)、A/Dサンプリング、レンジプロファイル生成、CFAR(定虚警率)検出器との連携が重要で、圧縮出力のサイドローブがCFARに与える影響を抑えるための重み付けやレンジマスクの戦略がとられる。高速A/D・FPGA/SoCにより長符号のリアルタイム整合フィルタやFFT相関が実現され、パルス圧縮とレンジ‐ドップラー処理を同一基盤で統合する設計が一般的になっている。liquidinstruments+3
5. サイドローブ低減と性能最適化
PSL/ISL低減のためのアプローチは、コード探索(ドロップレット/タイル符号などの組合せ最適化)、位相の連続最適化(多相符号やNLFMスペクトル整形)、整合フィルタ側の重み付け(Taylor, Kaiser, Dolph-Chebyshevなど)がある。二値符号では理論限界に近いPSLを目指すMPS(Minimum Peak Sidelobe)系列設計があり、ドップラー存在時のロバスト性も評価指標に含める研究が進む。多相最適化では、近年ポリフェーズ・バーカーと呼ばれる極低PSL系列の存在長が拡張的に報告され、ISL最適化との関係が整理されている。ittc.ku+4
重み付けは、主ローブ幅の拡大と引き換えにPSL/ISLを下げる典型的手段で、例えばTaylor重み付けで−40dB級のPSLを狙える一方、距離分解能が悪化するため、監視対象の密度や要求検出確率・虚警率と総合で決める。ドップラー感度は波形と整合フィルタの組で評価すべきで、LFMは一般にドップラー許容性が高いが、NLFMや複雑符号はドップラーでPSL/主ローブが劣化しやすいことがあるため、運用ドップラーバンドを踏まえた曖昧さ関数設計が不可欠である。ijstr+5
6. システム設計指標とレーダ方程式視点
圧縮後SNRは、送信パルスの時間帯域積TB(実効圧縮率)に比例して改善し、整合フィルタはAWGN下で出力SNRを最大化する。必要圧縮率は、目標とする距離分解能c/(2B)と探知距離(SNR要件)から逆算されるが、レンジサイドローブがCFAR検出に与える影響(偽ピーク、Swerling目標の検出率低下)を抑えるためのPSL/ISL仕様が併記される。パルス繰返し周波数(PRF)、帯域B、送信パワー、アンテナ利得は、レンジ‐ドップラー処理(CPI: coherent processing interval)と合わせて、探知性能・速度分解能・曖昧性の制約(レンジ/ドップラー折り返し)を決める。パルス圧縮出力はレンジ‐ドップラーFFTの前段に位置づけられ、CFARは圧縮後の雑音・クラッタ統計とサイドローブ床を前提に閾値を設定する。mathworks+3
7. 応用分野別の事例
レーダー分野では、気象・海上・航空管制・SAR/ISARでパルス圧縮が広く使われる。気象レーダでは位相符号化やLFMによって送信電力を落とさず分解能を高め、フェーズドアレイ化と両立させる検討が行われ、例えば短いバーカー符号の実装でISLが−4dB程度となる単純設計のベースライン評価が報告されている。海上監視や航空管制では、複雑なクラッタ環境下で低サイドローブとドップラー分離の両立が重要で、LFM+重み付けや長符号の最適化が用いられる。SAR/ISARでは、広帯域LFMを送信しマッチドフィルタでレンジ圧縮、方位方向はプラットフォーム運動で合成開口することで高分解能イメージングを行うのが定石である。ams.confex+5
超音波・ソナーでは、音速に応じた距離分解能向上と送信出力の抑制を両立するためにパルス圧縮が有効であり、LFMや位相符号化の適用で深達性と分解能のバランスを取る。線形FMのドップラー許容性は、移動体計測や流速測定でも有利に働く。レーザー分野における「パルス圧縮」は、CPA(チャープパルス増幅)後段で光学的に時間幅を圧縮する意味で用いられ、レーダ信号処理のパルス圧縮とは文脈が異なる用語であるため、混同せず整理が必要である。seti.ucla+5
8. 実験・シミュレーション手法
MATLABやシミュレータで、LFM生成、曖昧さ関数の可視化、整合フィルタ処理、レンジプロファイル評価を行うのが標準的な流れである。曖昧さ関数はゼロドップラーカット(自己相関)とゼロディレイカット(スペクトル包絡)を観察し、主ローブ幅・サイドローブ・ドップラーリッジの傾きから波形特性を評価する。実験系では、送受信路の位相・振幅リニアリティ、A/Dのダイナミックレンジ、タイミングジッタ、ローカル発振器の位相雑音などが圧縮性能に影響するため、較正信号の往復(レンジ・ドップラーでの基準ピーク)や記録・後処理のパイプラインを確立する。評価指標は、距離分解能、PSL/ISL、圧縮損失、ドップラー許容範囲、検出確率/虚警率(CFARでのP_d/P_fa)などである。mathworks+5
9. 最新動向と課題
デジタル受信機と高速A/Dの進展により、長符号や適応波形(コグニティブレーダ)の実用性が高まり、レンジ‐ドップラー同時最適化や環境適応的な波形選択が現実的になっている。マルチスタティックやMIMOレーダでは、相互干渉の少ない波形集合(低相互相関)設計や、目標/クラッタ状況に応じた遅延・ドップラー同時最適化が重要課題である。一方、実環境ではクラッタ・レイン、送受信機の非線形歪み、PAのAM/PM、サンプリングクロックの位相雑音、アンテナ/フロントエンドの帯域リップルなどが、圧縮サイドローブやミスマッチ損失を増やす要因となるため、波形の事前補償(プリディストーション)や受信での等化が必要になる。udrc.eng.ed+3
ドップラー許容性に関しては、LFMがベンチマークとして高い耐性を示すのに対し、NLFMはドップラーで主ローブ拡大や新規サイドローブの発生、ミスマッチ損失増加が起こりやすいと報告されており、用途の速度レンジに応じた選択が求められる。許容ドップラーの簡便指標や劣化の近似評価式が提案され、設計初期の比較指標として活用されている。wikipedia+3
10. 結論
パルス圧縮は、長パルスのエネルギーによる高SNRと広帯域変調による高分解能の両立を、整合フィルタを通じて実現する根幹技術であり、波形の時間帯域積TBが圧縮率と分解能を決める中核指標である。曖昧さ関数は、分解能(主ローブ幅)、サイドローブ、ドップラー耐性を統一評価する枠組みで、LFMは実装容易・ドップラー許容性のバランスに優れ、位相符号やNLFMはPSL/ISL低減の余地をもたらす一方でドップラーや実装要件とのトレードがある。実用設計では、整合フィルタの重み付けやウィナー化、プリディストーション、CFAR・レンジ‐ドップラー処理との統合で、PSL/ISL・分解能・SNRの最適バランスを図る。デジタル受信機の発展により長符号・適応波形が現実性を増し、マルチスタティック/コグニティブ化や環境適応的な波形‐受信機協調最適化が今後の主要テーマとなる。eit.lth+6
以上を踏まえ、ビジネスとしての波形設計・ハード/ソフト統合・検出アルゴリズム最適化は、目的分解能・探知距離・クラッタ環境・目標速度レンジを初期要求として明確化し、LFMを基準に、PSL/ISL要求が厳しい場合は重み付けや長符号最適化、ドップラー影響が大きい場合はLFM中心の設計とする、といった指針で要件駆動の選定を行うことが実行可能かつ低リスクなアプローチである。また、実機では非理想性の補償と校正、シミュレーション‐実測の往復で曖昧さ関数と検出性能を合致させる検証体制の構築が、量産・運用段階の品質と性能保証の鍵となる。its.ntia+4
- https://dsp-book.narod.ru/RSAD/C1828_PDF_C06.pdf
- https://www.mathworks.com/help/phased/ug/waveform-analysis-using-the-ambiguity-function.html
- https://udrc.eng.ed.ac.uk/sites/udrc.eng.ed.ac.uk/files/attachments/Introduction%20Radar%20signal%20processing.pdf
- https://its.ntia.gov/media/31078/DavisRadar_waveforms.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ambiguity_function
- https://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/eitn90/2020/lectures/lecture11.pdf
- https://www.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2017/papers/1570342388.pdf
- http://www.norbertwiener.umd.edu/crowds/documents/polyphase_pulse_comprssion_codes_with_optimal_sidelobes.pdf
- https://www.radartutorial.eu/08.transmitters/tx56.en.html
- https://ieeexplore.ieee.org/iel2/151/5217/00201102.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/Chirp_compression
- https://www.ittc.ku.edu/~sdblunt/papers/IEEE-TRS-Doppler_metric.pdf
- https://seti.ucla.edu/jlm/research/pfs/chirp.pdf
- https://www.ijstr.org/final-print/nov2019/Doppler-Effect-Analysis-Of-Nlfm-Signals.pdf
- https://liquidinstruments.com/application-notes/matched-filter-with-fir-filter-builder/
- https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/123417.pdf
- https://www.mathworks.com/videos/pulse-waveform-basics-visualizing-radar-performance-with-the-ambiguity-function-1680765164982.html
- https://www.youtube.com/watch?v=UCir6mOW2OU
- https://www.osti.gov/servlets/purl/1716574
- https://taylorandfrancis.com/knowledge/Engineering_and_technology/Industrial_engineering_&_manufacturing/Ambiguity_function/
※本ページは、AIの活用や研究に関連する原理・機器・デバイスについて学ぶために、個人的に整理・記述しているものです。内容には誤りや見落としが含まれている可能性もありますので、もしお気づきの点やご助言等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※本ページの内容は、個人的な学習および情報整理を目的として提供しているものであり、その正確性、完全性、有用性等についていかなる保証も行いません。本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことによって発生した損害(直接的・間接的・特別・偶発的・結果的損害を含みますが、これらに限りません)について、当方は一切責任を負いません。ご利用は利用者ご自身の責任でお願いいたします。